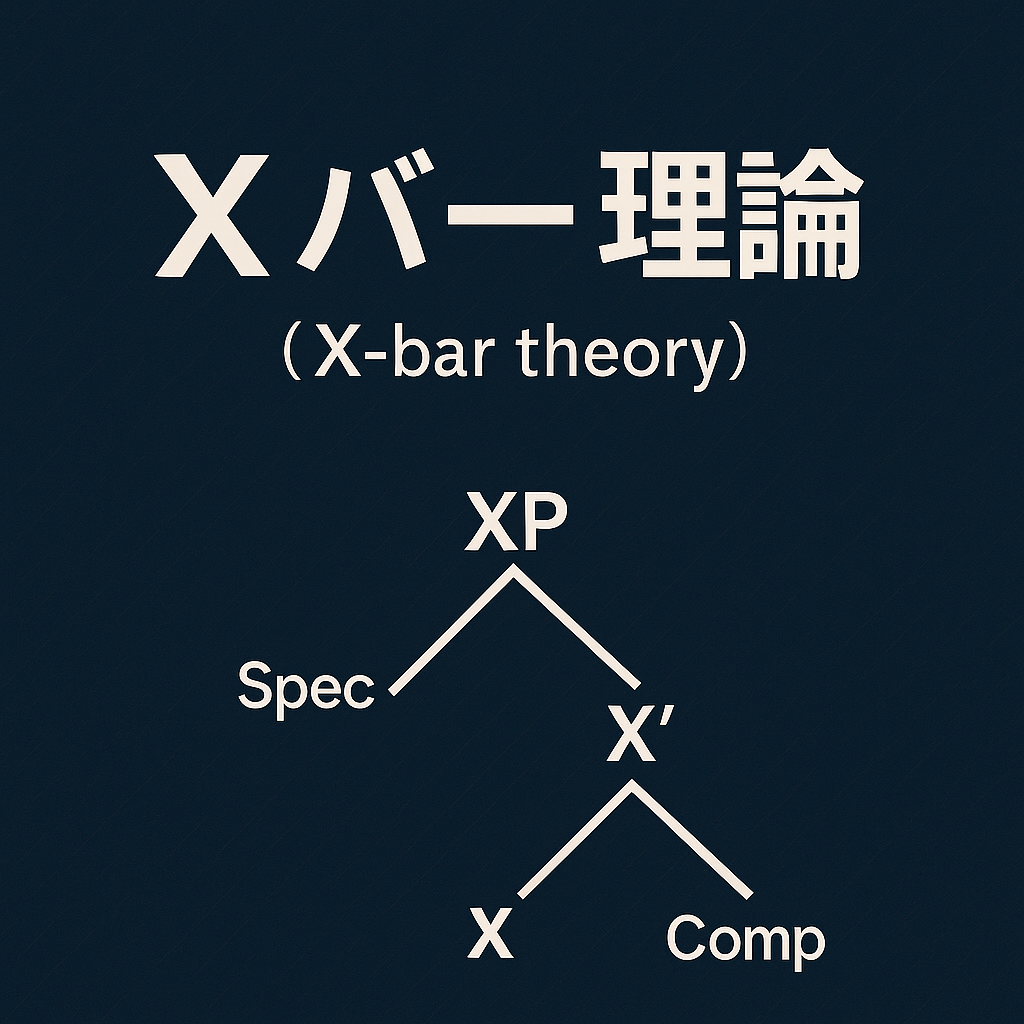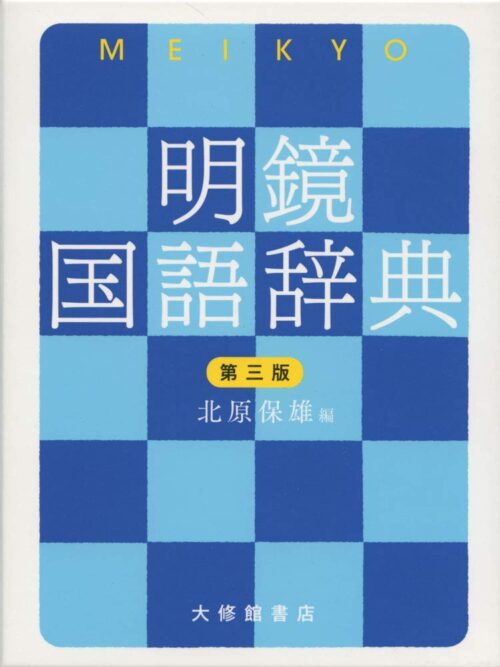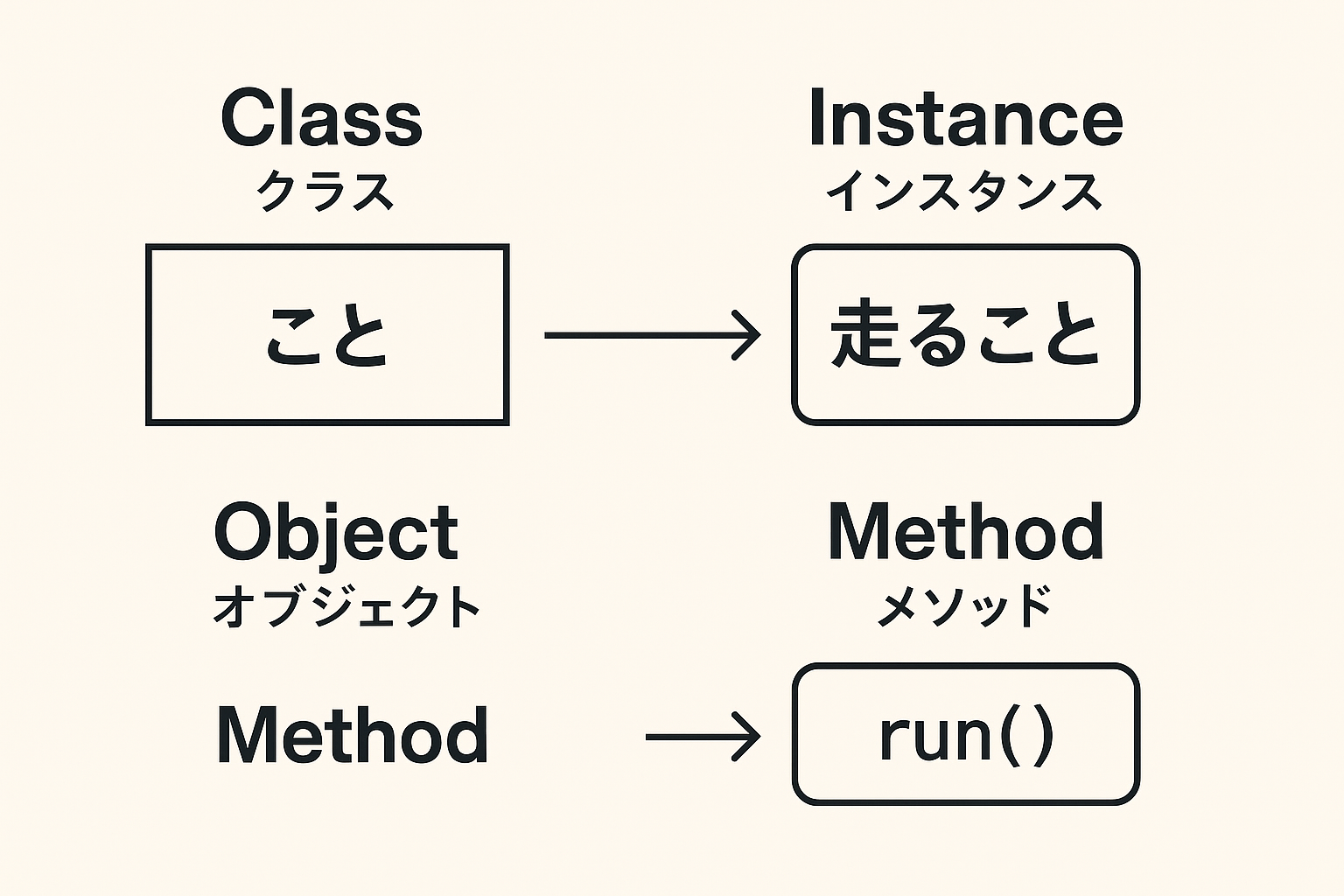Xバー理論(X-bar theory) は、チョムスキーの理論体系「生成文法」の中で、1970年代に発展した 統語構造の普遍的な型を説明する理論 です。
この理論によって、異なる言語を「同じ構造の変形(word order)」として説明できるとしました。
🔹 基本的な考え方
- 言語ごとに語順は違っても、句(phrase)の内部構造には普遍的なルールがある。
- その普遍ルールを「Xバー理論」で定式化した。
- 「X」とは任意の品詞(N=名詞、V=動詞、A=形容詞など)を指す。
Xバー構造
「句」の内部構造
Xバー構造は、「句」は3層でできている、と考えます。
- X⁰(ヘッド / Head)
- 句の中心となる語。
- 例:動詞句なら「食べる」、名詞句なら「本」
- X’(中間層 / intermediate projection)
- 補語(complement)を伴う層。
- 例:「本を読む」の「読む」に対する「本を」
- XP(句全体 / maximal projection)
- 句の最大単位。修飾語や指定部(specifier)を含む。
- 例:「太郎が本を読む」の「太郎が〜」の部分がspecifier
図式
句全体(XP)は、一般的にこのような、3層のXバー構造になっています。
XP
/ \
Spec X'
/ \
X⁰ Comp
動詞や名詞(主要部)などを最小単位として句全体は次のように成立します、
- 句全体(XP)
- X’ + Spec で全体の句が仕上がります。
- Spec(specifier / 指定部):主語や限定詞など、句の左側に来る要素
- X’ + Spec で全体の句が仕上がります。
- 最小の句(X’)
- Head(X⁰)+Comp で成立します。
- Head(X⁰):主要部(動詞・名詞など)
- Comp(Complement / 補語):主要部に必須で従属する要素(目的語など)
- Head(X⁰)+Comp で成立します。
具体例
XPの種類
XPは「句の型」を表す総称です。
- 任意の句(phrase)全般を指す抽象記号。
- 「X」の部分に「品詞」が入り、具体的な「インスタンス」となります。
インスタンスによって、節の中の句の役割が把握できます。
事例
「太郎が本を読む」
- 動詞句 VP の場合
- Head(V⁰)=「読む」
- Complement=「本を」
- Spec=「太郎が」
図にすると:
VP
/ \
NP V'
(太郎が) / \
V⁰ NP
(読む) (本を)
意義
- これにより、英語・日本語・フランス語など異なる言語を
「同じ構造の変形(word order)」として説明できる。 - 例:
- 英語: 「She [eats apples]」
- VP=NP(She)+ V’
- V’=V⁰ (eats)+ NP(apples)
- 日本語: 「彼女が [リンゴを|食べる]」
- VP=NP(彼女が)+ V’
- V’=NP(リンゴを)+ V⁰ (食べる)
- → 主要部(head / V⁰)の、位置が違うだけで、Xバー理論的には同じ構造になっています。
- 英語: 「She [eats apples]」
まとめ
- Xバー理論は、句は必ず「ヘッド(X⁰)+補語+指定部」という共通構造を持つ、という仮説。
- 言語の差は「語順の違い(ヘッドが前か後か)」にすぎない、と整理できる。
- これが、後の ミニマリスト・プログラム(1990年代以降の生成文法)へとつながっていきます。