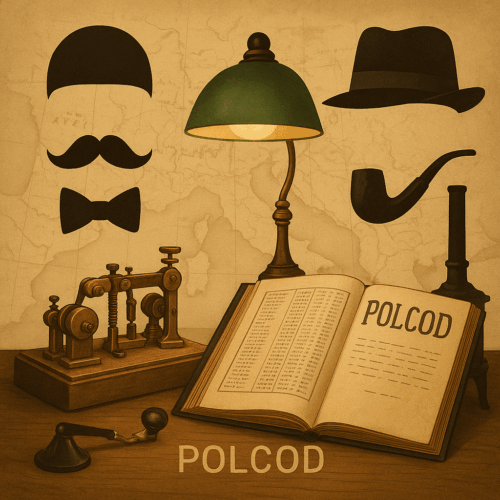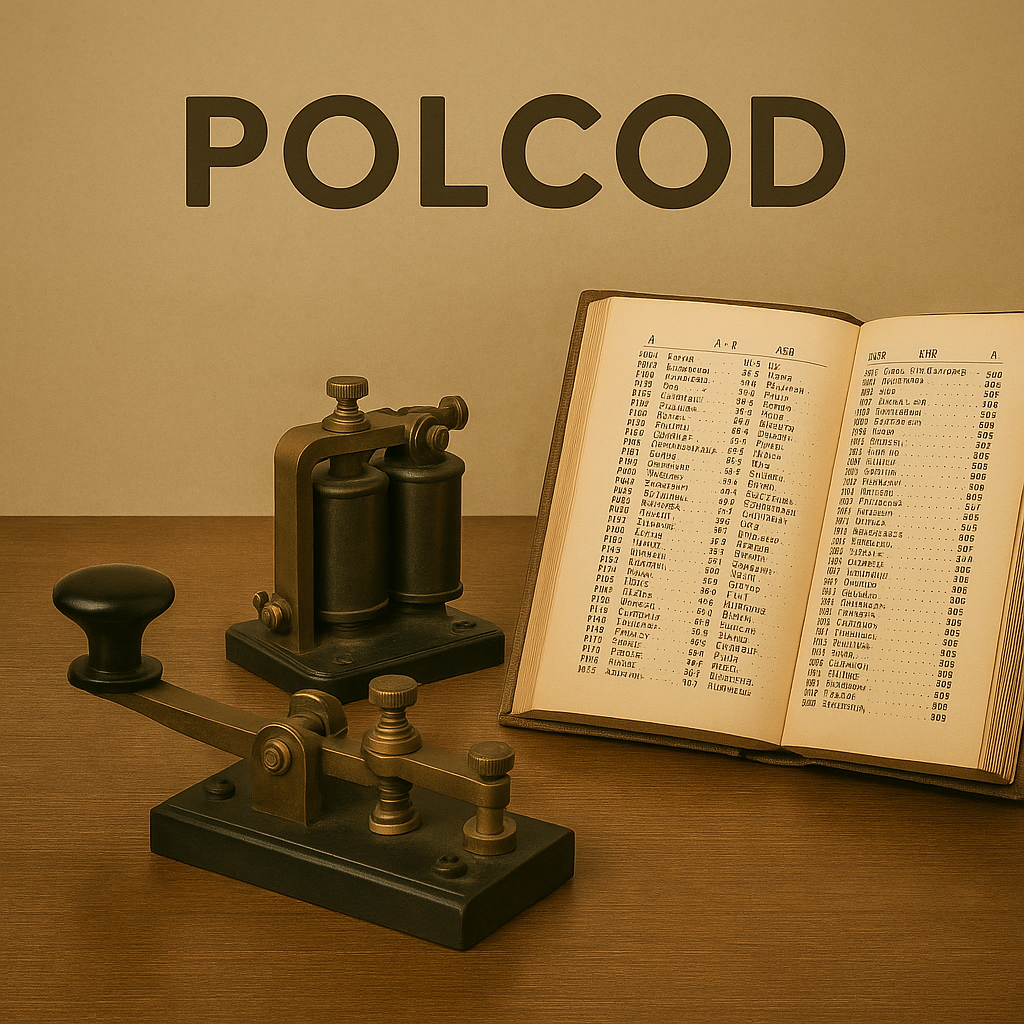〜クリスティが書かなかった「POLCOD」〜
1930年代、ヨーロッパではすでに電報と電話が社会の神経のように張りめぐらされていた。
その中で、二人の名探偵――エルキュール=ポワロとジュール・メグレ――は、まったく異なる「通信の世界」に生きていた。
メグレの世界:官僚的ネットワークの中の探偵
ジョルジュ・シムノンの『怪盗レトン』(1931)では、メグレが冒頭で受け取る二通の電報が、物語の扉を開く。
rédigé en polcod, langage international secret utilisé dans les relations entre tous les centres policiers du monde.
「ポルコード(polcod)」――世界各国の警察本部が共有する秘密の暗号通信言語。
この一語によって、読者はただの殺人事件ではなく、ヨーロッパ規模の国際犯罪網へと導かれる。
メグレが向き合うのは、個人の犯行ではなく、国境を越える情報と組織の流れだ。
火の気のない冬のオフィスで、鋳鉄ストーブをいじりながら、彼は電報を読む。
その手もとにあるのは、もはや「手紙」ではなく「信号」である。
ポワロの世界:個人の心理が紡ぐ通信
対してアガサ・クリスティの作品に「polcod」は登場しない。
もちろん、ポワロは警察の人間ではないため、国家警察間の通信文を直接受け取ることはできないからだ。
スコットランド・ヤードのジャップ主任警部は「polcod」を受け取ってるはずだが、具体的にそれポワロと共有する場面は見たことがない。
彼女の世界では、通信はあくまで人と人の心理的なつながりを表すものとして描かれているのだろう。
- 『そして誰もいなくなった』では、電報が偽装の道具となる。
- 『ナイルに死す』では、ホテルへのテレグラムが不吉な伏線となる。
- 『ビッグ・フォー』では、世界規模の暗号電報が出てくるが、それは警察ではなく「陰謀組織」のもの。
ポワロが追うのは人間心理のコードであって、国家の通信線ではない。
彼にとって事件の鍵は、人間の発言、沈黙、表情――それぞれが送受信する「感情の信号」なのである。
同時代の二つのリアリズム
メグレとポワロは、どちらも1920〜30年代という同じ時代に生きている。
しかしその世界の構造はまったく異なる。
| 観点 | メグレ(シムノン) | ポワロ(クリスティ) |
|---|---|---|
| 通信の性質 | 官僚的・国際的ネットワーク(CIPC・polcod) | 個人的・心理的な通信(手紙・電報・沈黙) |
| 事件の範囲 | 社会構造と制度 | 人間関係と心理 |
| 象徴 | ストーブと電報 | 紳士的礼儀と推理の会話 |
| 世界観 | 「現実に接続された制度の内部」 | 「閉ざされた人間ドラマ」 |
シムノンのリアリズムは、人間を制度の歯車の中に置く冷たいリアリズム。
クリスティのリアリズムは、人間の内側にある秩序と倫理を信じる温かいリアリズム。
「polcod」は、その違いを一語で象徴している。
通信のない場所にこそ真実がある
第1次対戦後の1930年代――世界は電線でつながり始めていた。メグレは電報を読み、ポワロは沈黙を読む。
どちらも同じ「通信の時代」に生きながら、ひとりは制度の通信網を、もうひとりは人間の心の通信を読み解く。
シムノンが描いたのは「信号の時代」クリスティが描いたのは「沈黙の時代」
と言ってもいいのではなかろうか