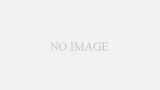ジョルジュ・シムノン『サン=フォリアン教会の首吊り男』の冒頭には、異国の駅で迷うひとりの旅人が登場する。
彼はドイツ語を理解できず、標識も読めないまま、うっかり「一等客用のレストラン」に入り込み、何度も行ったり来たりしたあげく、ようやく「三等客用のビュッフェ」にたどり着く。
この短い場面には、1930年代ヨーロッパの鉄道文化と階級社会が凝縮されている。
鉄道における「等級社会」
当時のヨーロッパの鉄道では、列車そのものが一等・二等・三等に分かれていただけでなく、駅構内の待合室や食堂も同じく「等級別」に区分されていた。
食堂の等級区分
| 区分 | 主な利用客 | 設備・雰囲気 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 一等(Première classe) | 上流階級、外交官、実業家 | 絨毯敷き・白布のテーブル・給仕付き | 入室時に一等切符の提示 |
| 二等(Seconde classe) | 中産階級、教師、商人 | 簡素だが椅子席あり | 二等切符 |
| 三等(Troisième classe) | 労働者、兵士、旅人 | 木製ベンチや立ち食いカウンター | 三等切符 |
入口には係員が立ち、切符の等級を確認してから入室させるのが通例だった。
そのため、誤って高等級のレストランに足を踏み入れると、
すぐに注意され、追い出されることもあった。
「ビュッフェ des troisièmes」という空間
三等客用のビュッフェ(buffet des troisièmes)は、高級感とは無縁の庶民的な食堂だった。
立ち食いカウンターにパン、チーズ、ゆで卵、コーヒー、安ワイン。
壁は白塗り、椅子は金属製、照明は裸電球。
一方で、旅人たちのざわめきと湯気に満ちたその場所には、一等レストランにはない温かい雑踏の匂いが漂っていた。
■ シムノンの描いた「迷子の男」
この場面での“最初の旅人”は、異国の地で居場所を失い、
切符の等級を通じて、自分の社会的立場の狭さと不安を体現している。
言葉も通じず、階級の線引きが壁となり、
ようやく辿り着いた場所でさえ、彼は席に着けない。
それは、彼の孤独と罪悪感を象徴するかのような静かな演出だ。
鉄道文化が語る社会の階層
1930年代の鉄道は、単なる交通手段ではなく、
当時の社会階層を可視化する「移動する社会縮図」だった。
一等の白布と銀食器、三等の紙コップとパンくず。
その落差の中に、シムノンは「人間の哀しみ」を描き込む。
だからこそ、このささやかな食堂の迷子の場面が、
作品全体の運命と孤独の予兆として印象的に響くのである。