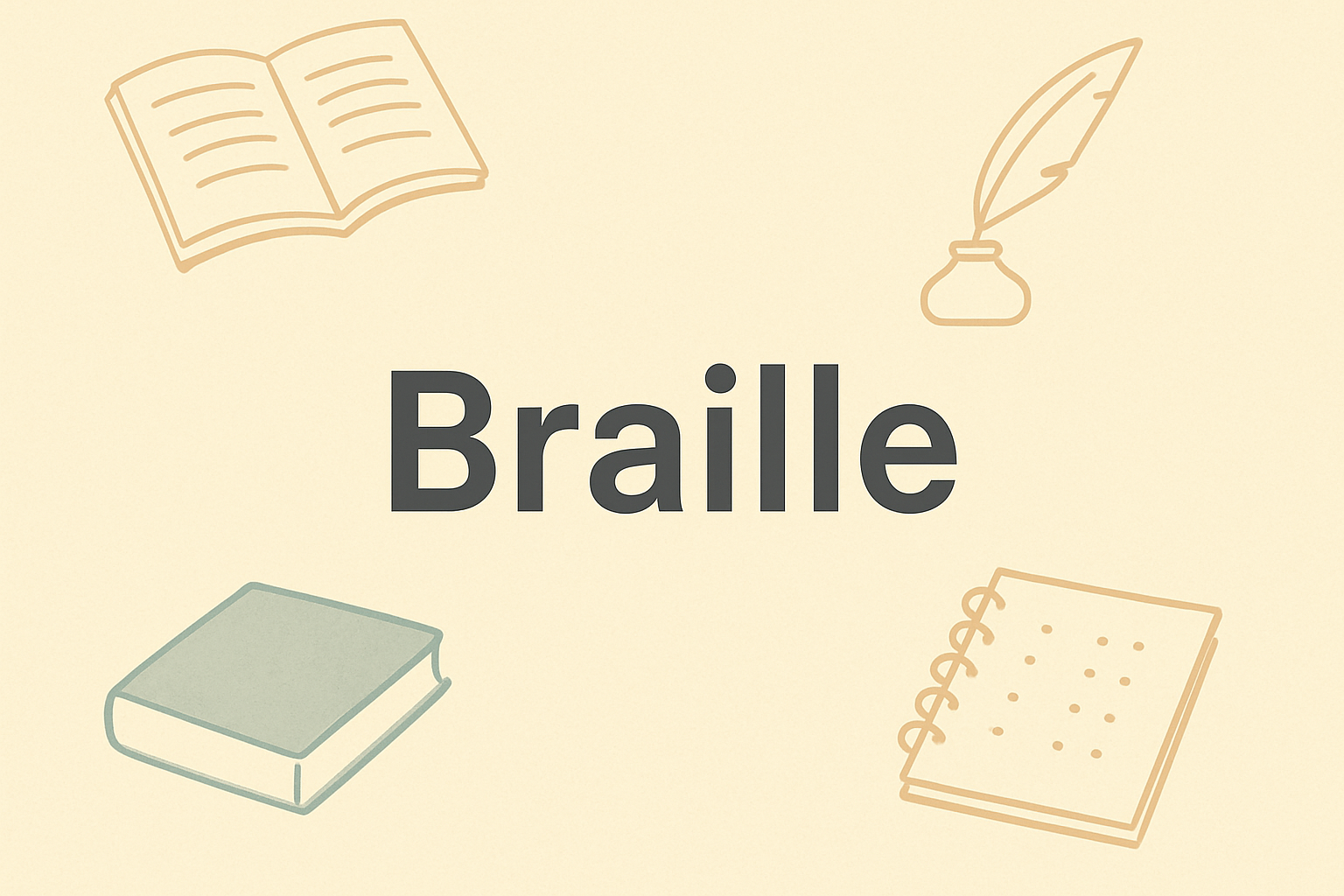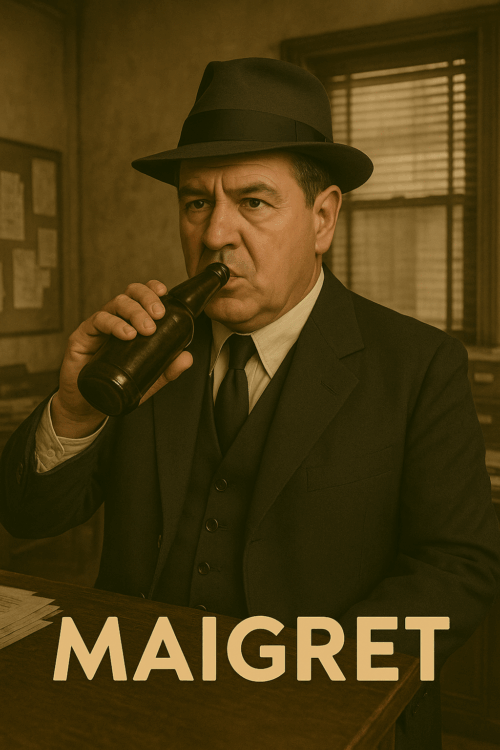戦前のモンマルトル ― 芸術家の丘
19世紀末から20世紀初頭にかけて、モンマルトルは「芸術家の村」として知られていた。
- 格安の家賃やアトリエ
- 独特の村落的雰囲気
- ボヘミアン文化と自由な空気
これらが画家・詩人・音楽家を引き寄せ、ピカソ、モディリアーニ、ユトリロ、ロートレックらが活動した。
とくに「バトー=ラヴォワール(洗濯船)」のアトリエは、キュビスムを生んだ象徴的拠点であった。
第一次世界大戦による空白
1914年に大戦が勃発すると、若い芸術家たちの多くが徴兵され、モンマルトルのコミュニティは空洞化する。
- 兵役や国外避難による人材流出
- パリの生活困難化
- 芸術活動の停滞
戦前の「創作の丘」としてのモンマルトルは、事実上の機能停止に追い込まれた。
戦後の変化 ― 観光地化と商業化
戦争が終わり人々が戻ったとき、モンマルトルには「過去の伝説」が残されていた。
「ピカソがいた丘」「ユトリロの描いた坂道」という記憶が観光資源となり、キャバレーやカフェがその名声を商品化した。
- ピカソやユトリロが活動した「聖地」として観光客を惹きつける
- キャバレーやカフェが「芸術の思い出」を商品化し、歓楽街へと変貌
- 家賃の上昇で、若い芸術家が住みづらくなった
そして、フランス政府は、大戦で疲弊した国家財政を立て直すため、観光産業を奨励した。
観光局の整備、鉄道や宿泊施設の拡充、国際博覧会の開催などを通じて観光客を呼び込む政策が進められた。
さらに1923年にはサクレ=クール寺院が完成。これは大戦犠牲者の慰霊や国の贖罪を象徴する国家的事業であり、同時にモンマルトルを芸術家の村から「観光と歓楽の街」へと姿を変えた。
モンマルトルは「芸術の伝説」「歓楽街」「サクレ=クール寺院」を武器に、自然に観光拠点として成長したのである。
芸術の中心の移動 ― モンパルナスへ
1920年代になると、芸術の新しい中心はモンパルナスに移った。
- 低家賃のアトリエ(ラ・リューシュなど)
- ドーム、ロトンド、クーポールといったカフェ文化
- 国際的芸術家(スペイン、イタリア、ロシア、ユダヤ人など)の集積
こうして「エコール・ド・パリ」と呼ばれる多国籍の芸術運動が花開いた。
モンマルトルの二重性
第一次世界大戦は、モンマルトルを「芸術の創造の場」から「観光と歓楽の街」へと変容させる契機となった。
芸術家の実際の活動拠点はモンパルナスへと移り、モンマルトルには「過去の栄光」という観光資源が残された。
この二重性――歓楽と伝説、観光と衰退――が、1930年代のモンマルトルを舞台にした作品に深みを与えている。
小説の舞台としてのモンマルトル
シムノンの小説に登場する1930年代のモンマルトルは、まさにこの「二重の顔」を背負っていた。
- 観光客で賑わうキャバレーや大聖堂
- その裏に潜む貧困や移民の路地
- 華やかな表舞台の陰で横行する売春と犯罪
物語に描かれる「夜道を歩く女性たちを狙う連続殺人事件」が、モンマルトルに限定されているのは偶然ではない。
芸術の聖地としての輝きが色あせ、観光と歓楽に覆われた街は、同時に「不安と恐怖の舞台」としても現実味を持っていた。
ポイント
第一次世界大戦は、モンマルトルを芸術の村から観光と歓楽の街へと変貌させた。
シムノンが描くモンマルトル連続殺人事件は、この歴史的変容を背景に、都市の光と影を凝縮している。
芸術の残像と歓楽の喧噪、そしてその陰に潜む犯罪。
それこそが、1930年代パリを舞台にしたメグレ事件簿において、モンマルトルが持つリアリティなのである。