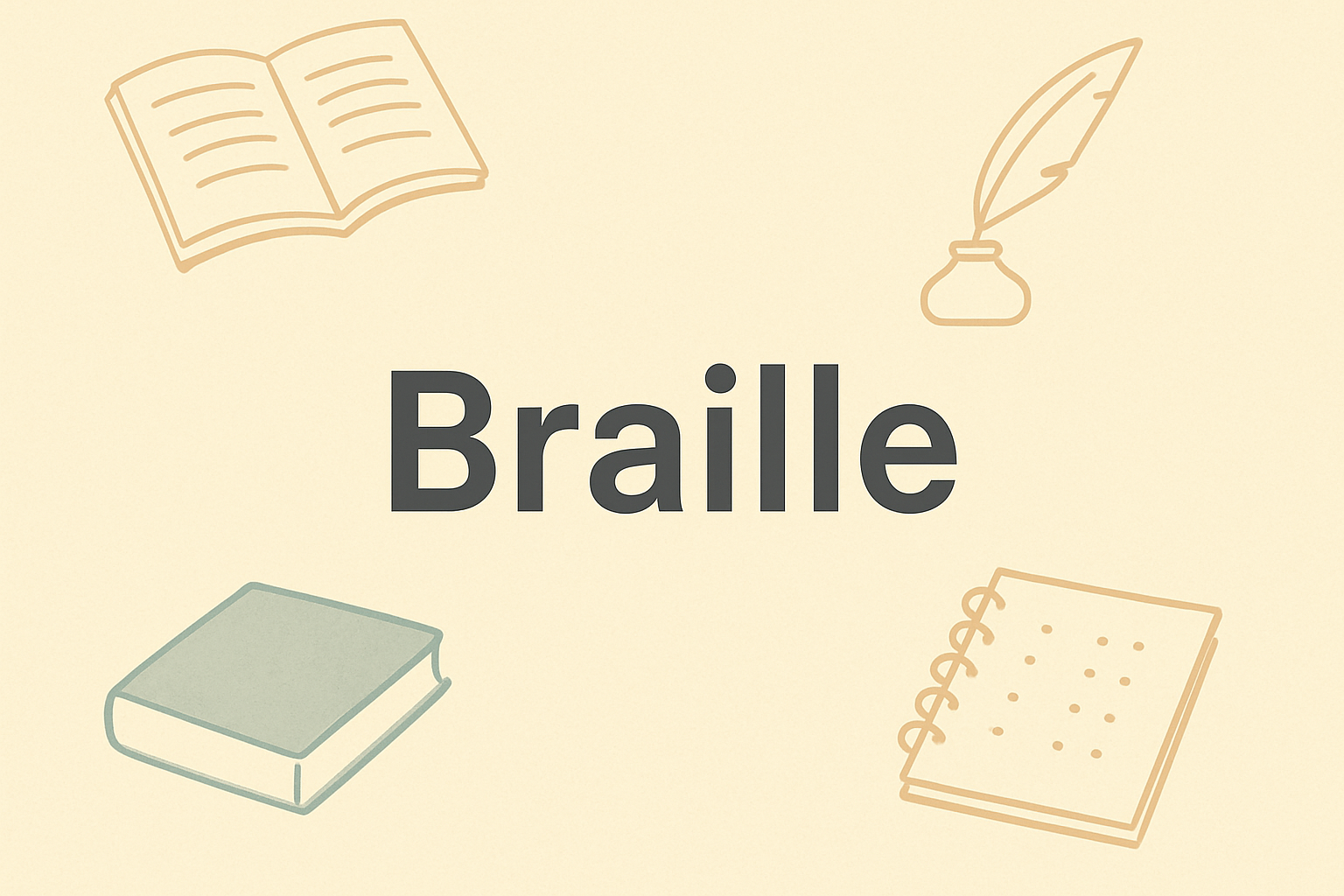「アパート」と「フラット」
イギリスでの flat
クリスティの時代、ロンドンの flat は「集合住宅の一室」を意味しました。
19世紀末のタウンハウスを分割して貸し出す形や、新しい集合住宅の一部屋を指すのが一般的でした。
つまり「フラット」はごく日常的な都市の住まいを表す言葉です。
日本に入ったのは「flat」ではなく「apartment」
同じ集合住宅でも、アメリカでは apartment が普通です。
明治後期から大正期にかけて、日本で広まったのは アメリカ経由の英語でした。
- 留学生や教科書がアメリカ式
- 貿易や移民もアメリカとの結びつきが強かった
そのため、日本では「集合住宅=apartment」と認識され、略して「アパート」と呼ぶようになったのです。
flat ではなく apartment が定着した理由
初期はイギリス式だった
- 幕末に最初に日本に英語を教えたのはイギリス人教師や宣教師で、当時の教材はイギリス英語寄りでした。
- 例えば、長崎や横浜の外国人居留地で雇われた教師は多くがイギリス人。
- 明治初期の外交や法体系もイギリスを強く意識していたため、当初はイギリス流が主流でした。
教育の主流はアメリカへ
- 明治10年代以降、日本が本格的に英語教育を制度化したとき、教師の多くはアメリカ人宣教師でした。
- プロテスタント宣教師たちは聖書翻訳・学校設立(同志社、明治学院など)を通じて、若者にアメリカ式の発音や語彙を教えました。
- 東京帝国大学でも、文学や思想はイギリス・フランスも影響しましたが、実務としての法学・政治学・工学ではドイツ語、そして英語は「米語」が標準化していきました。
アメリカ留学と教科書
- 明治後半〜大正期、日本政府はアメリカへ多数の留学生を送りました。
- 彼らが持ち帰った知識や教材が、そのまま「標準英語」として広まった。
- 出版された英語教科書の多くはアメリカのテキストを翻訳・改変したもので、イギリス式の “flat” より、アメリカ式の “apartment” が浸透しました。
経済と移民の影響
- 大正時代、日本の最大の輸出市場はアメリカ。
- 生糸・綿織物・茶などの主要品は、ほとんどアメリカ西海岸へ送られていました。
- また、日本人移民の多くがアメリカ(特にハワイ・カリフォルニア)に渡ったため、帰国した人々がアメリカ式の言葉や生活習慣を伝えたのです。
イギリスとのギャップ
- 当時のイギリスは、外交・軍事上は、日英同盟(1902〜1923)による協力関係がありましたが、教育・文化にはほとんど影響はありません。
- イギリスは、ロシアに対する「同盟国」ではあっても「生活文化を輸出する国」ではなかったのです。
- 一方アメリカは宣教師・映画・留学・移民を通じて、庶民レベルにまで英語文化を浸透させました。
ポイント
日本で「アパート」が使われるのは、
- アメリカ英語の apartment が直接輸入されたこと、
- 都市化に伴う木造集合住宅にその言葉が当てられたこと、
- イギリス英語 flat が文化的に入ってこなかったこと、
この3つが重なったためです。
戦後に生まれた「マンション」
当時の日本の都市は住宅不足。
実際に建てられたのは 木造二階建ての簡易集合住宅 でした。
そして戦後、日本に鉄筋コンクリート造の集合住宅が登場。
さらに、賃貸ではなく分譲される高級な集合住宅も現れます。
そこで、「木造集合住宅」(アパート) と区別するために日本独自の用語として「マンション」が使われました。
- アパート=安価な集合住宅
- マンション=高級集合住宅
本来 apartment には高級住宅の意味もあるのに、日本では「安価な共同住宅」のイメージに限定されてしまいました。この意味での「マンション」は日本だけでの呼称ですので、日本独自の二分法が定着することになります。