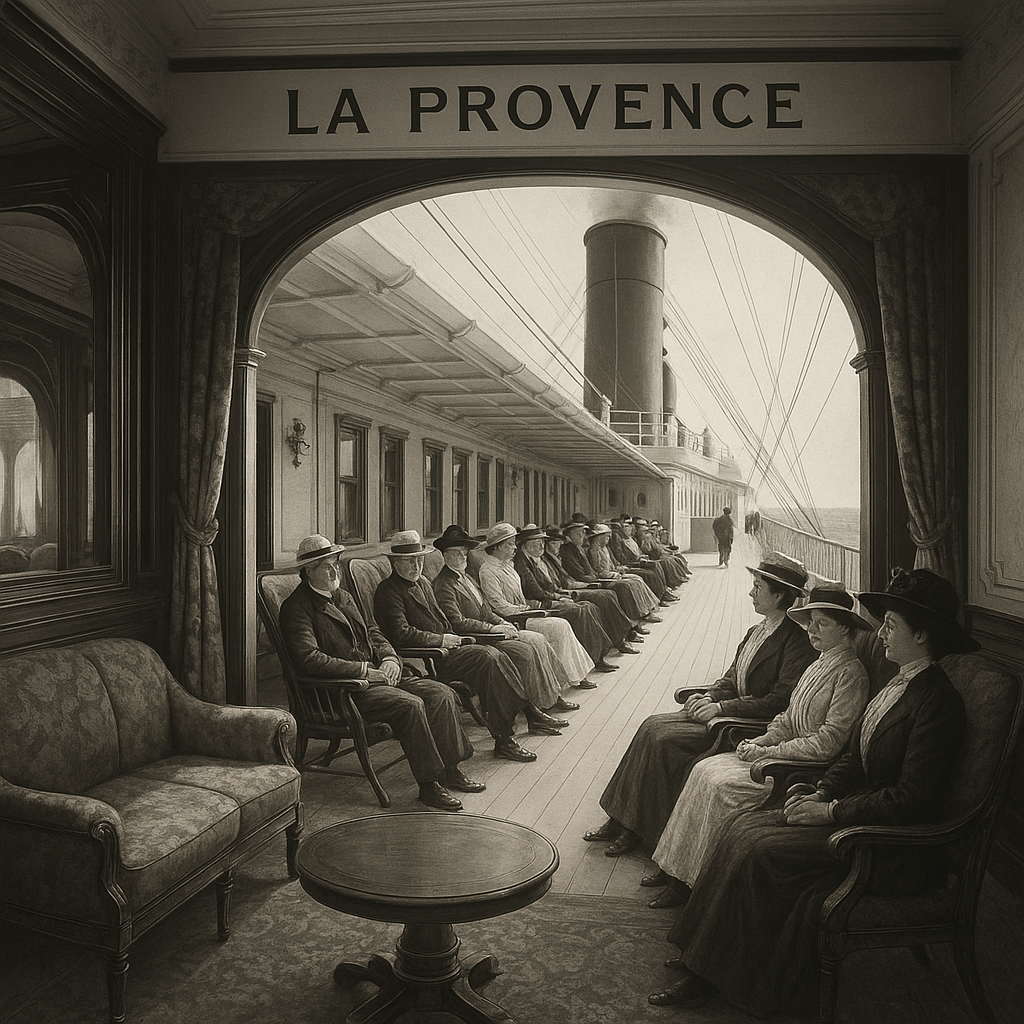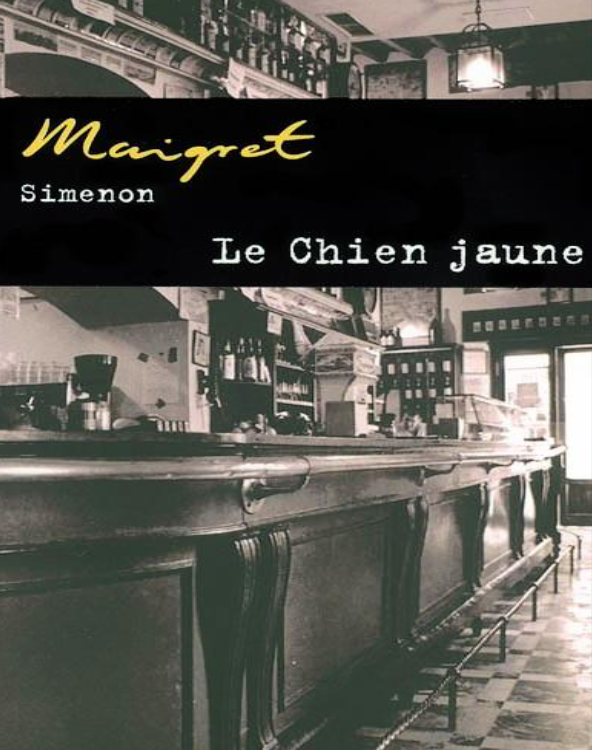Et le soir on sut qu’il avait été convoqué par le commandant.
そして|その夜、|彼が|船長に|呼び出されていたことが|分かった。
とてもよく出てくる表現である、
「〜いたこと」「〜いること」という、補助動詞「いる」を含んだ名詞句を受ける、形式名詞「こと」の文節である。
分かち書きの考え方
「呼び出されていたことが」(11拍)を、どのように区切るか問題となる。
- 『点訳の手引き』では、次のとおり、3つに区切る。
- |彼が|船長に|呼び出されて|いた|ことが|分かった。
一方、ラボ流分かち書きでは、3つの考え方がある。
- 原則「補助動詞、形式名詞の前では区切らない」を遵守する。
- しかし、「11拍」は読み手の負担が過大であるため、例外的適切な場所で区切るべきである。
- リズム(拍数)を重視
- 7拍以下になるように、補助動詞「いた」の前で区切る。
- 「彼が|船長に|呼び出されて|いたことが|分かった」
- 7拍以下になるように、補助動詞「いた」の前で区切る。
- 誤読(意味のまとまり)を重視
- 「名詞句」を続け書きして、名詞句を受ける形式名詞「こと」の前で区切る。
- 彼が|船長に|呼び出されていた|ことが|分かった。
- 「名詞句」を続け書きして、名詞句を受ける形式名詞「こと」の前で区切る。
意味のまとまり
「いたこと」の前で区切ると、「6+5」拍となって、リズムは良くなる。
しかし、この文節全体の意味のまとまりは
「彼が船長に呼び出されていた」
という事象、つまり「こと」である。
したがって、「2番」のように「呼び出されて|いた」のように区切って、「いたこと」を続けるのは、意味のまとまりを壊してしまい、、誤読の可能性が生じてしまうのだ。
よって、意味のまとまりを重視し、誤読を防止するのであれば、「3番」のように「呼び出されていた」を一続きに書くことが推奨されるのである。
Et le soir on sut qu’il avait été convoqué par le commandant.
そして|その夜、|彼が|船長に|呼び出されていた|ことが|分かった。
もっとも、ラボ流分かち書きの「7拍基準」に抵触する。ただし、「七拍基準」はあくまで、リズムを重視して、触読の負担を軽減するためのものである。
したがって、誤読のリスクを冒してまで遵守すべき原則ではないと考える。
つまり、誤読を防止するためであれば、8拍以上の続け書きをすることを許容するのである。
ポイント
区切る箇所の優先順位は
誤読防止(意味のまとまり重視)> リズム(読み手の負担軽減重視、7拍基準)
ということである。
今後、ラボ流分かち書きで、長い文節で区切る優先順位は、「形式名詞」>「補助動詞」ということを、「7拍基準」の例外的な準則としたい。
(備考)『点訳の手引き』でも、「補助動詞」の前で区切ることは推奨していないのである。
(追記:12月21日)
Et le soir on sut qu’il avait été convoqué par le commandant.
そして|その夜、|彼が|船長に|呼び出されていたことが|分かった。
7泊基準は、警戒ラインであって、必ず区切るという万能基準ではないということを踏まえると、11拍でも、読み手の負担にならない場合は続け書きする。
この部分の構造は「呼び出されて」に力点があり、後続の補助動詞、形式名詞の意味は薄いと考えると、このように続け書きすることも考えられる。
ただ、その後に続く「わかった」 という動詞が、文章全体の主文であることから、力点が重く、前述のように、形式名詞「ことが」の前で区切ることも考えられる。
いわゆる『関係代名詞』的な考え方である。
Et le soir on sut qu’il avait été convoqué par le commandant.
そして|その夜、|彼が|船長に|呼び出されていた|ことが|分かった。
つまり、文章全体から、区切る箇所を判断すると
『彼が|船長に|呼び出されていた』⇨ 一旦区切る
構文として、「そのことがわかった」と続く。
ということになる。