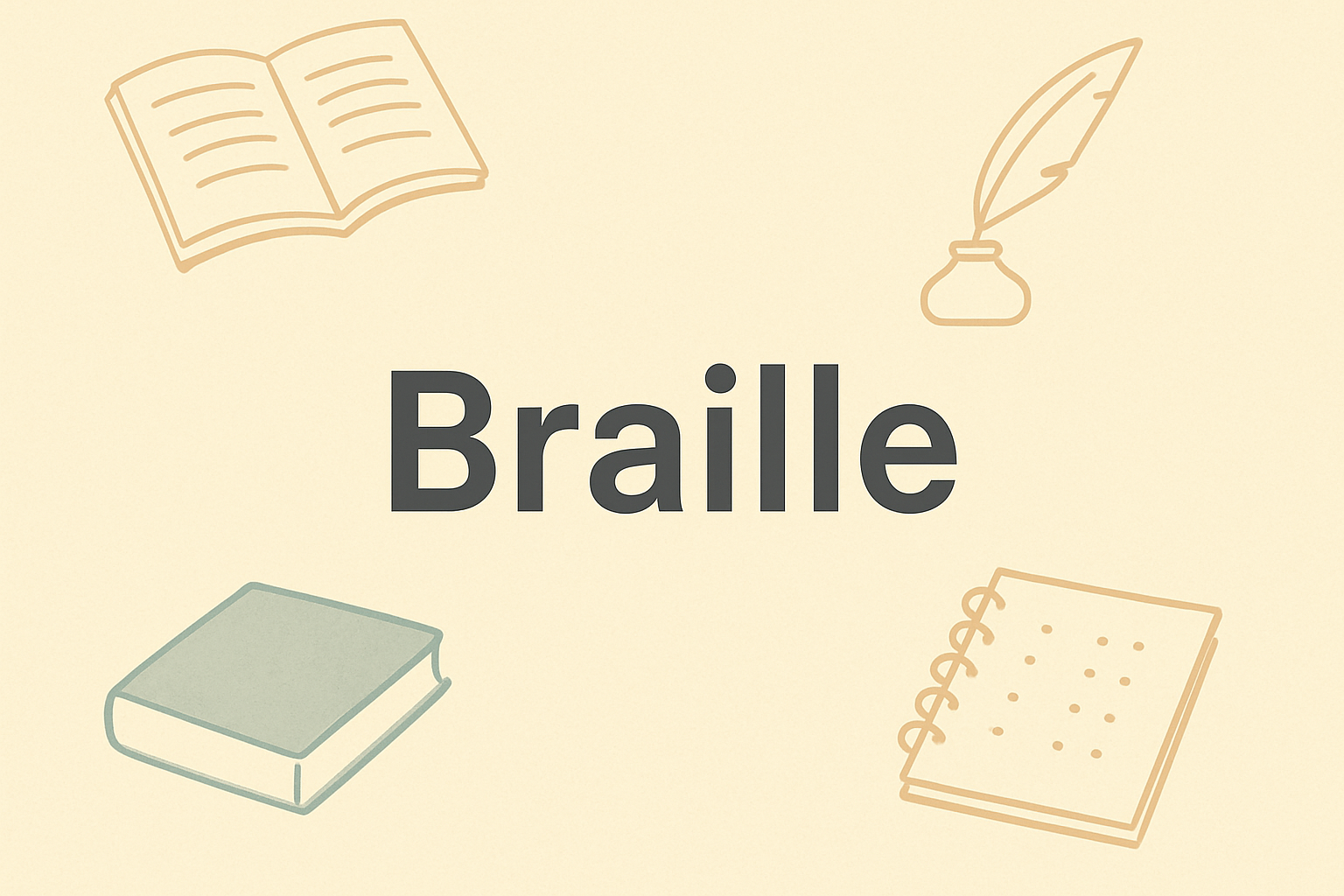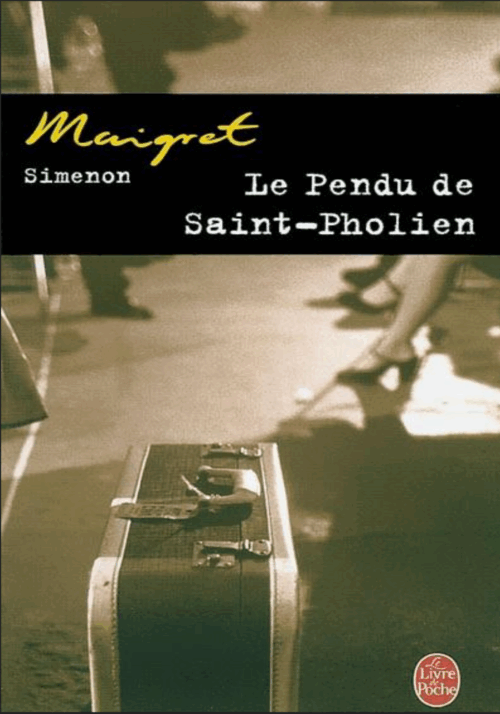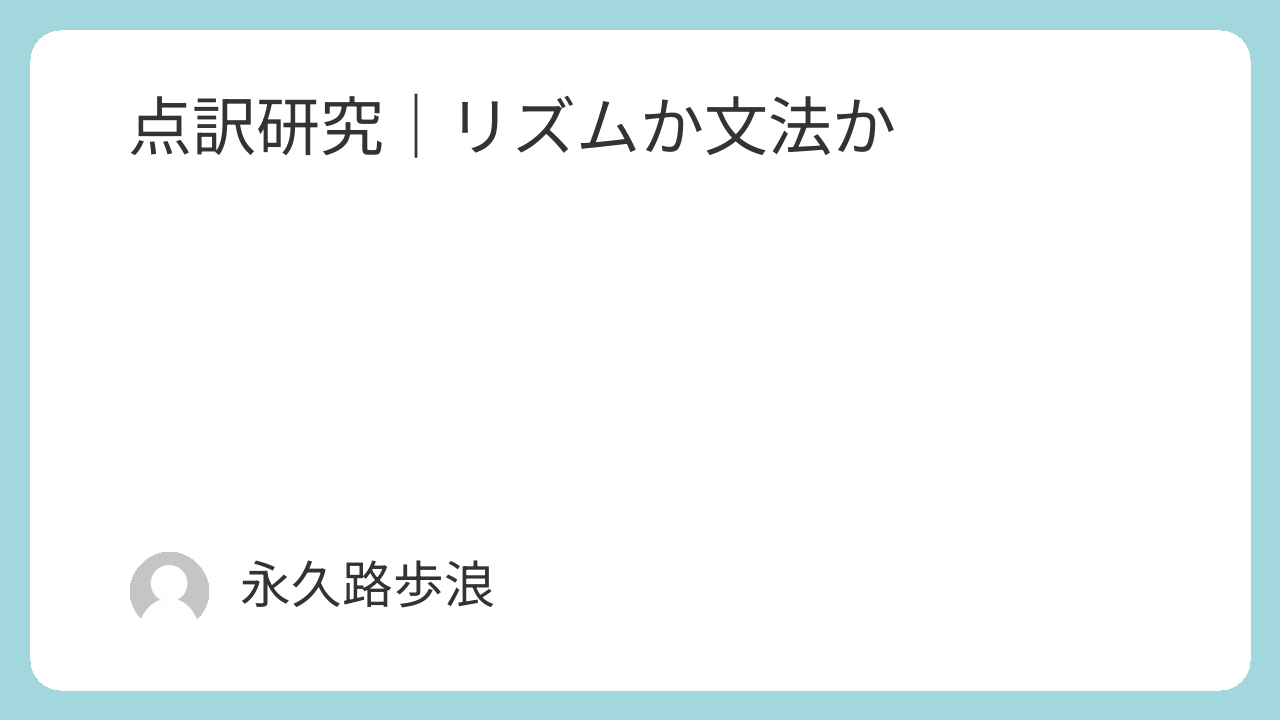明鏡国語辞典に「のだ」と言う見出しがありました。
ラボ流の原則「連語の内部では区切らない」=「区切る場合はその前で区切る」に基づけば、かなり乱暴な区切り方になります。
しかし、文節分かち書きで長い文節で困ったときに、慣れてくれば読み手も点訳者も楽かもしれません。
以下、デジタル大辞泉、明鏡のコピペです。
用例を、ラボ流7拍基準を元に「のだ」の前で区切ってみました。
赤色アンダーラインが、区切る対象となったものです。
連体形につくので自然な区切りとなり、区切る根拠として使えます。
デジタル大辞泉
「のだ」
- 〘連語〙《準体助詞「の」+断定の助動詞「だ」》
- (1) 理由や根拠を強調した断定の意を表す。
- 「赤信号を|無視して|走るから|事故を|起こすのだ」
- (2) 話し手の決意、または相手に対する要求・詰問の意を表す。
- 「なんとしても|その|夢を|実現|させるのだ」
- (3) 事柄のようすやあり方を強調して説明する意を表す。
- 「この|谷は|一年じゅう、|雪が|消えずに|残っている|のだった」
- (補説) 話し言葉では「んだ」の形をとることが多い。→のです
- (1) 理由や根拠を強調した断定の意を表す。
「のである」
- 〘連語〙
- 《準体助詞「の」+連語「である」。話し言葉では「んである」とも》
- 連語「である」に同じ。
- 「大臣が|そう|断言した|のである」
- 「彼自身の|したこと|なんである」
- 「で‐あ・る」
- 〘連語〙《断定の助動詞「なり」の連用形「に」に接続助詞「て」、補助動詞「あり」の付いた「にてあり」の音変化》
- (1) 断定の意を表す。…だ。
- 「兄は|作家であり、妹は|ピアニスト|である」
- 「タダ|ツキセヌモノワ|涙デアッタ」〈天草本平家・二〉
- (2) (「のである」 「なのである」の形で)説明する意、または強く決意を表明する意を表す。
- 「人間とは|孤独なもの|なのである」
- 補説 「である」は鎌倉時代に発生し、室町時代に発達した語で、「じゃ」 「だ」はこれから出たもの。現代では、文章語・演説口調の常体として用いられる。
明鏡
「のである」
- [連語]
- 「のだ」①②の改まった言い方。[参照]のだ①②
- [参考]丁寧な言い方では「のであります」となる。
「のだ」
- [連語]
❶前に述べたことやその場の状況の原因・理由・帰結などを、解き明かすような気持ちで提示する。言い切りの形には断定の気持ちがこもる。
「熱が|ある。||風邪を|ひいたのだ」
「高齢|なのだから|無理しないほうが|いい」(判定詞と共に区切ってみた)
「暇を|持てあましたから|遊びに|来たのだろう」
「煮え切らないのは、|要するに、|やる気が|ないのだ」
❷次に述べることの原因・理由・前提などを表す。
「知らなかった|のなら(ば)、|許してやろう」
「久しぶりに|会ったのだが、|あまり|変わっていなかった」
「山田君を|探している|のだが、心当たりは|ないか」
❸強い主張を表す。
「気にするな。||これで|いいのだ」
「いいか、|お前は|何も|見なかった|のだぞ」
❹《意志的な動作を表す動詞に付いて》決意・命令を表す。
「俺が|やるのだ」
「さ、|早く行くのだ」
❺《疑問詞とともに使い、下降のイントネーションを伴って》強く詰問する気持ちを表す。
「何を|しているのだ」
「今ごろ|どこから|来たのだ」
❻《「…のだった」の形で》過去のことを詠嘆的に表す。
「ようやく平和が|訪れた|のだった」
❼《「…のだった」の形で》悔やむ気持ちを表す。…しておけばよかった。
「こんなことなら|予約しておく|のだった」
[参考]使い方
⑴活用語の連体形に付く。
⑵話し言葉では「んだ」となることが多い。改まった言い方では「…のである」、丁寧な言い方では「…のです」となる。[参照]のである・のです