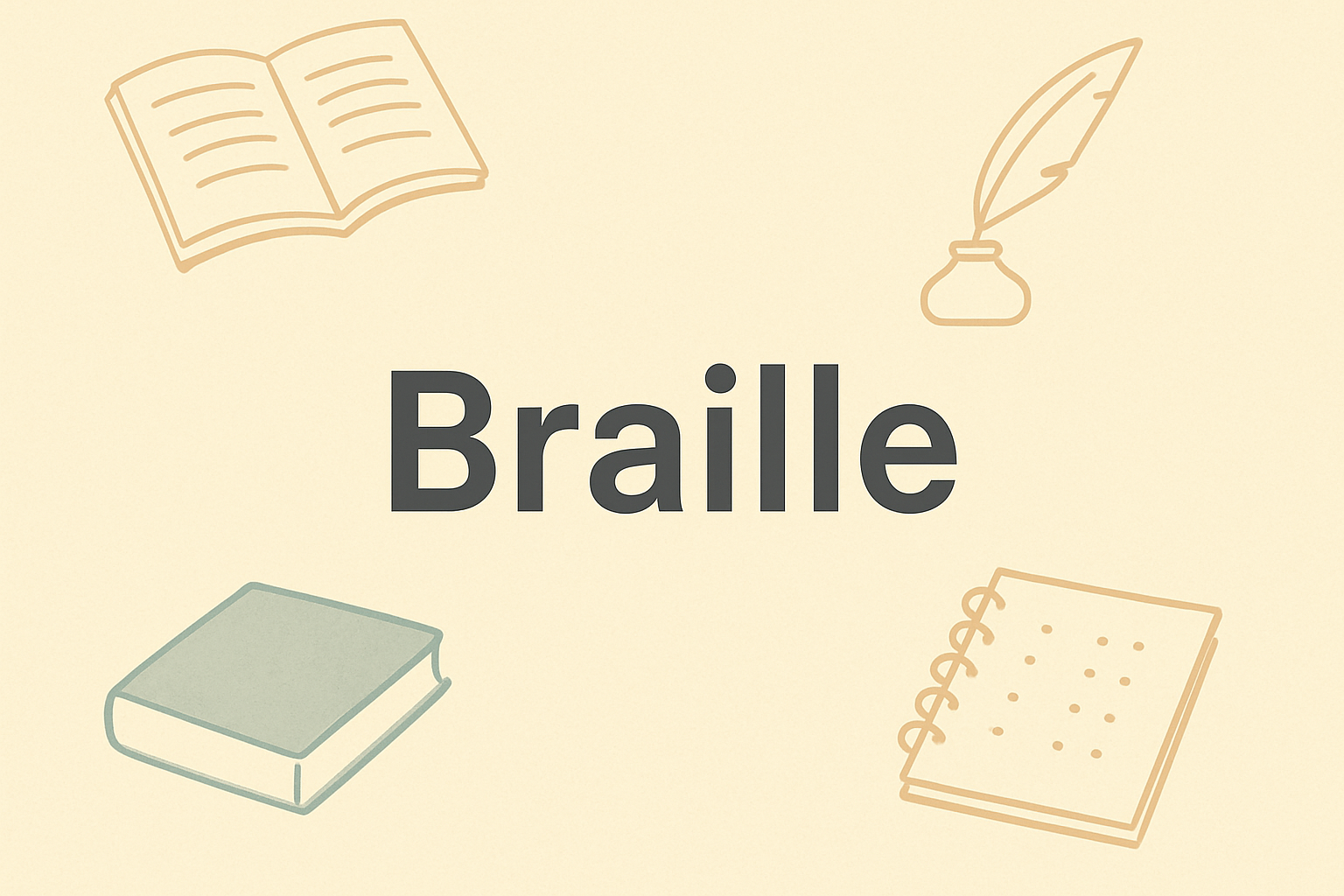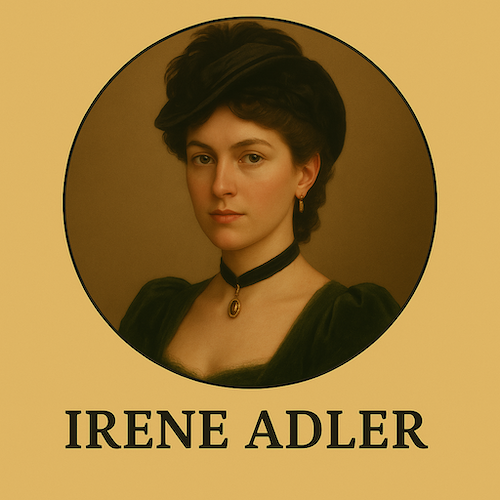座っていたそうだ
『ベンスン殺人事件』を翻訳・点訳していると、こんな文章が出てきました。
服を着たまま、リビングのお気に入りの椅子に、座っていたそうだ」
点訳する場合、「座っていたそうだ」を、どう処理するか問題となります。
『点訳の手引き』準拠
『点訳の手引き』にしたがって、区切って書くとこうなります
服を|着たまま|リビングの|お気に入りの|椅子に|座って|いたそうだ。」
本来、『日本点字表記法』の第一の原則「文節分かち書き」であれば、複合動詞「座っていた」+助動詞「そうだ」と解釈し、「座っていたそうだ」と続け書きしたいところです(『手引き』P.76)
しかし「〜ていた」のような「テ形動詞」の「テ」は、連用形の語幹に助詞の「て」がついたものとみなし、「〜て|いた」と補助動詞の前で区切ることになります(『手引き』P.77「備考」)。
しかも、『補助動詞も動詞』『補助動詞も自立語』という「文法解釈」に従うことを絶対視している(3回くらい書かれている)ので、音韻変化や省略形などを除いて『続けることができる』といった例外規定はありません。
つまり、これ以外の表記法は『点訳の手引き』では「間違い」とされるのです😩
誤読の可能性の回避
しかし、この文脈では次のような誤読が生じる恐れがあります。
「すわって|いたそうだ」→ 「座って|痛そうだ」
『椅子に上に座っていて、痛そうに見える』と解釈することは、普通にあり得ます🤪。
しかしラボ流では、文節が8拍以上になった時は、「そうだ」の前で区切ることを許容します。
「座っていたそうだ」→「すわっていた|そうだ」
その根拠は、
- 「形式名詞+判定詞」とみなすことによって、その前で区切ることができる。
- 助動詞「〜そうだ」は、国語学上の歴史的な成り立ちとして「〜さう(様子・ありさまを表す名詞)・なり』と説明される。
- ラボ流で基本書としている『基礎日本語文法』では、「て」は「活用語尾」とされている。
- 上記の「テ形動詞」の「助詞説」は、「学校文法」上の解釈に過ぎない。
- 「座っている」は複合動詞と解釈し、続けて書くことができる。
- 表音式(しゃべり言葉)では、「座っていた」を続けた方が、「すわって|いた」と区切るよりも、自然に聞こえる(→抑揚分かち書き参照)
- 「すわって|いたそうだ」と区切って読んでいると、本当に「痛そう」に聞こえてきます!
ポイント
辞書に基づく文法解釈は、主に「学校文法」「教育上の文法」ですので、公的な点字図書館で「同質の点字図書を数多く揃えるため」には有用でしょう。
しかし、ラボ流では「読み手の誤読を避けること」を第一とし、「同質の点字図書を揃えること」は、特に目的とはしていません。
文法解釈は補助的なものとして柔軟に解釈することで、読みやすい点字作品を揃えることができると考えています。
追加事例
川が|まるで|コンロの|上の|鍋の|お湯のように|湯気を|あげて|イルカのようで|あった。🐬
あえてカタカナで書きましたが、本来は平仮名「いるかのようで」です。
川がイルカに見える!?という意味ではありません。
ラボ流では、補助動詞「いる」「ある」は続けて書くこと、助動詞「ようだ」は区切って書くことを許容しているので、誤読防止のために、次のように区切ります。
川が|まるで|コンロの|上の|鍋の|お湯のように|湯気を|あげているかの|ようであった。