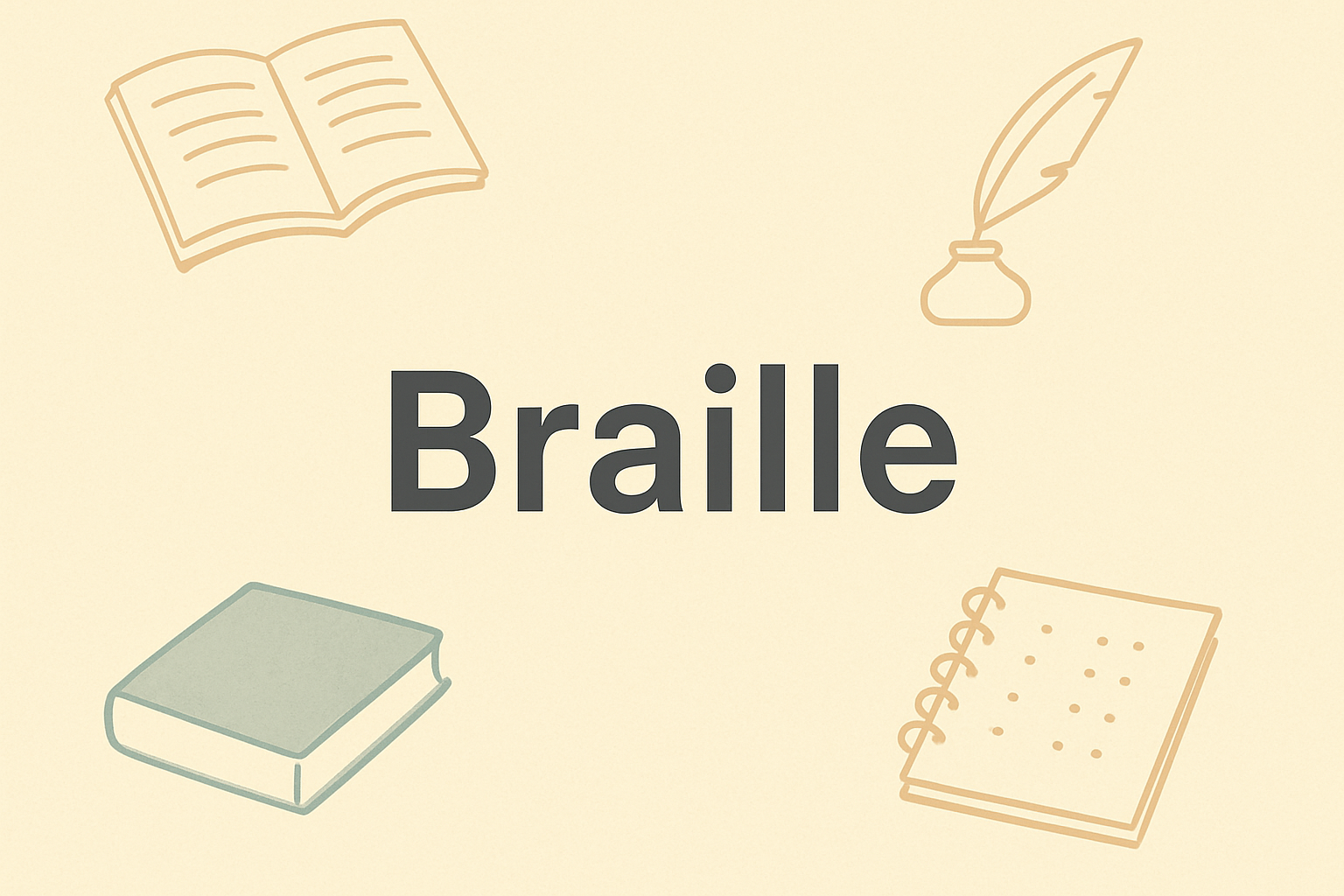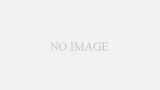国語文法における「の」の二つの用法
ハイブリッドラボを進めていると『〜のである』『〜のだろう』という文章で表現したいのですが、多くが8拍以上となってしまい、なかなか使いづらく、泣く泣く言い換えて対処することが多です。、
ただ、リズム上「の」の前が、体言または用言の連体形や終止形で終わっていること多い様です。
つまり、触読で意味を理解する上では、そこで区切っても読み手の意味の理解の妨げになるようなことはないのでは?と思えてきました。
そこには、国語文法上の「の」の二つの役割が関係しているので、まとめてみました。
(1) 準体助詞「の」
- 品詞:助詞(付属語)
- 働き:直前の用言や句を名詞化して体言相当のはたらきを持たせる。
- 意味:自立的な意味はない。
例:
- 青いのが好きだ(=青いもの)
- 君が書いたのを読みたい(=君が書いたもの)
「青い」と「の」名詞と助詞の関係なので、「文節分かち書き」の原則では区切ることはできません。
(2) 形式名詞とされる「の」
- 一部の文法学では、「の」を形式名詞(=「こと」「もの」と同じく名詞的」)とみなす立場がある。
- 例:行くのが好きだ(=行く「こと」が好きだ)
- 例:怖かったのです(=怖かった「こと」です)
- この場合「の」は、形式名詞「こと」や「もの」と言い換えることが可能です。
- そこで、名詞そのものとみなすことで、自立語として文節を形成することができ、直前で区切っても文法的に成立することになります。
『点訳のてびき』での扱い
『点訳のてびき 第4版』では、
- 「の」を形式名詞とはせず、一律に助詞(準体助詞)として扱い、形式名詞と扱うことはありません。
- したがって点訳の上では「青いの」「行くの」など、すべて続け書きしなければなりません。
ラボ流の方針
ラボ流では『手引き』を踏まえつつ、自然なリズムも考慮して以下のように整理します。
原則
- 「の」はすべて助詞扱いとし、前で区切らず続け書き。
- 例:
- 青いのが|好きだ
- 行くのが|好きだ
- 例:
例外(許容)
ラボ流では「続け書き」を基本としつつ、続けて書くと読み手の負担となるような場合は、「の」を形式名詞とする国語文法の立場を根拠に、例外的に「の」の前で切ることを許容することとする。
- 文が 8拍以上で自立語が一つしかなく、他に自然な区切りがない場合に限り、「の」の前で区切ることを許容する。
- 例:「通り過ぎる|のだろう」(通り過ぎる|ことだろう)
- 「通り過ぎる」が複合動詞で一つの意味のまとまりなので区切ることはできない。そこで、「の」が形式名詞「こと」の代用として「形式名詞」の前で区切る。
- 例:「通り過ぎる|のだろう」(通り過ぎる|ことだろう)
その他の理由
- 「のだろう」は「連語」として扱われる場合があり、「通り過ぎるの|だろう」「〜のだ|ろう」とすることは慣用性において意味の理解を妨げ、また発音上リズムが悪い。
- デジタル大辞泉
- の‐だろ◦う〔―だらう〕〘連語〙《準体助詞「の」+断定の助動詞「だ」の未然形+推量の助動詞「う」。話し言葉では「んだろう」とも》
- デジタル大辞泉
- 「通り過ぎ|るのだろう」は、「る」までが活用語尾なので、文法上説明がつかない。
- 『点訳の手引き』は形式名詞「の」を、用例として挙げていないだけと考えることもできる。
ポイント
- 『手引き』: 「の」は一律助詞扱い → 続け書き。
- ラボ流: 原則は同じ。ただし読み手の負担となるときだけ「の」の前で区切ることを許容(根拠=国語文法上は形式名詞とされる立場がある)。