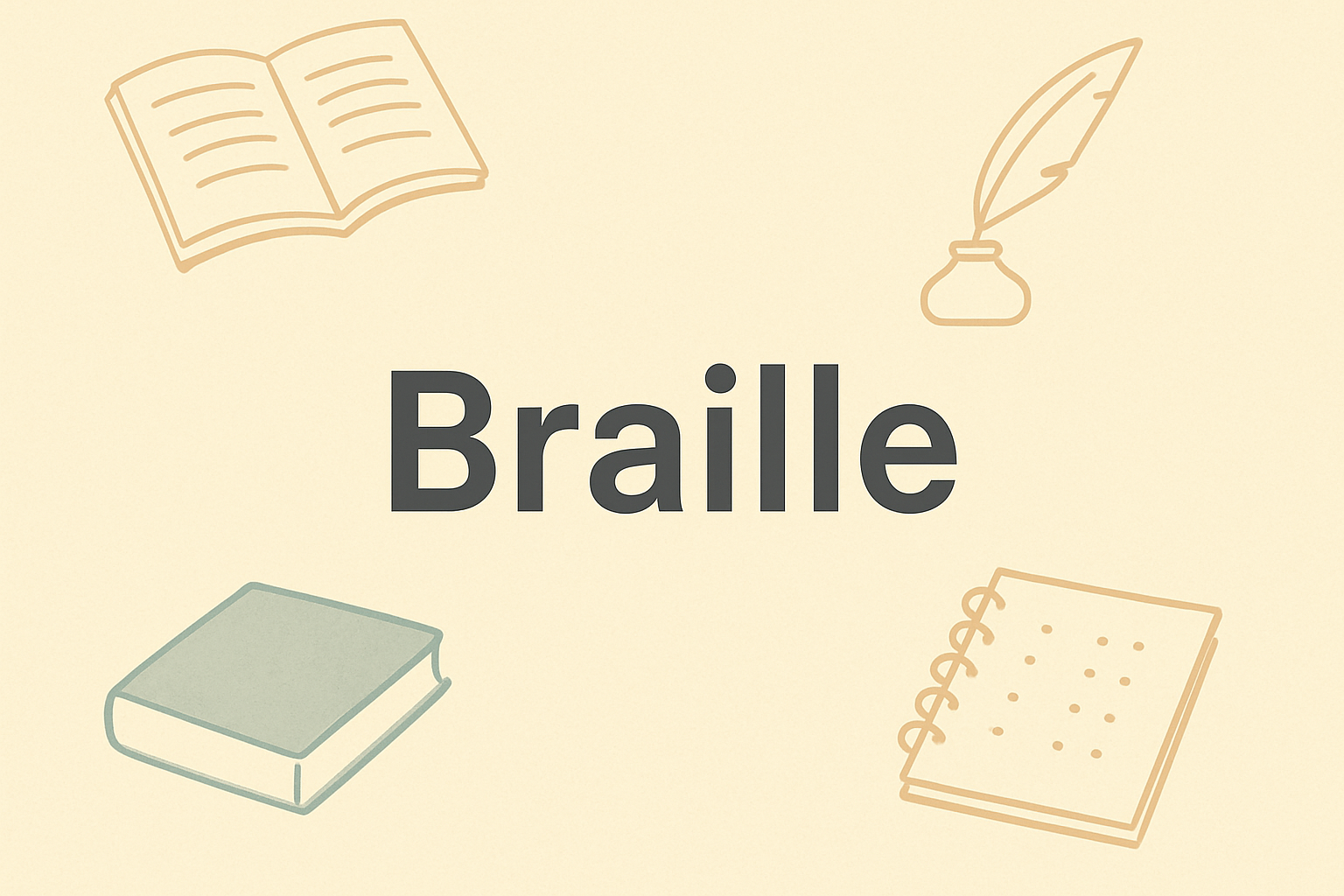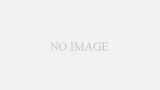点字図書室で感じた「目的と手段のすり替わり」
趣味として点訳を続ける、自分なりのスタンス
先日、点字図書室を訪ねた。
私は当初、点訳ボランティアとして活動できればと考え、講習に参加した。
しかし、実際に目にした現実は、自分が思い描いていた「読み手のための点訳」とはかけ離れていた。
そこでは「読み手にどう伝わるか」よりも、「手引きに従って登録すること」や「活動を続けること」そのものが目的になっていた。
肝心の「視覚障害者の方にとってどうか」という視点が、後景に追いやられているように感じられた。
ボランティアは本来、目的を果たすための手段である。
生計を立てる仕事でもなく、報酬が出るわけでもない。
であればこそ、読み手に「読めてよかった」と思ってもらえることこそが唯一の報酬であるはずだ。
だが、現場にはその姿勢が見えなかった。
そのため、私は意味を見いだせず、講習を途中で退会した。
結果として「奉仕としての点訳」ではなく、「趣味としての点訳」に傾いていくしかなかったのである。
理屈にこだわる理系の私にとって、点字は言語という文系の分野ではあるものの、石川倉次さんが、理屈に基づいて作ったシステマチックで有用性のある仕組みの文字と理解している。
シャーロック=ホームズの「踊る人形」の暗号文の如きである。理屈にのっかっているの、知らない人間でもで解読しようとすれば解読できる文字であろう。
翻訳の段階から触読を意識し、言葉が指先で伝わるよう工夫をすることは、とても面白い作業だと感じている。
だからこれからは、誰かに奉仕するためではなく、自分の楽しみと記録のために点訳を続けていく。
その記録が未来の誰かにとって参考になり、共感につながれば、それで十分だ。
仕事やボランティア活動としてではなく、あくまで趣味として歩む点訳。
今回の体験は、それを改めて心に刻むきっかけとなった。
そして気づいたのは、実践編で感じた違和感の背景に、この「制度としての点字図書室」の姿があるということだ。
だからこそ私は、「こんな使い方する手引きなんていらない」という立場をより確信し、自分の翻訳と点訳を楽しむ道を選んでいきたい。