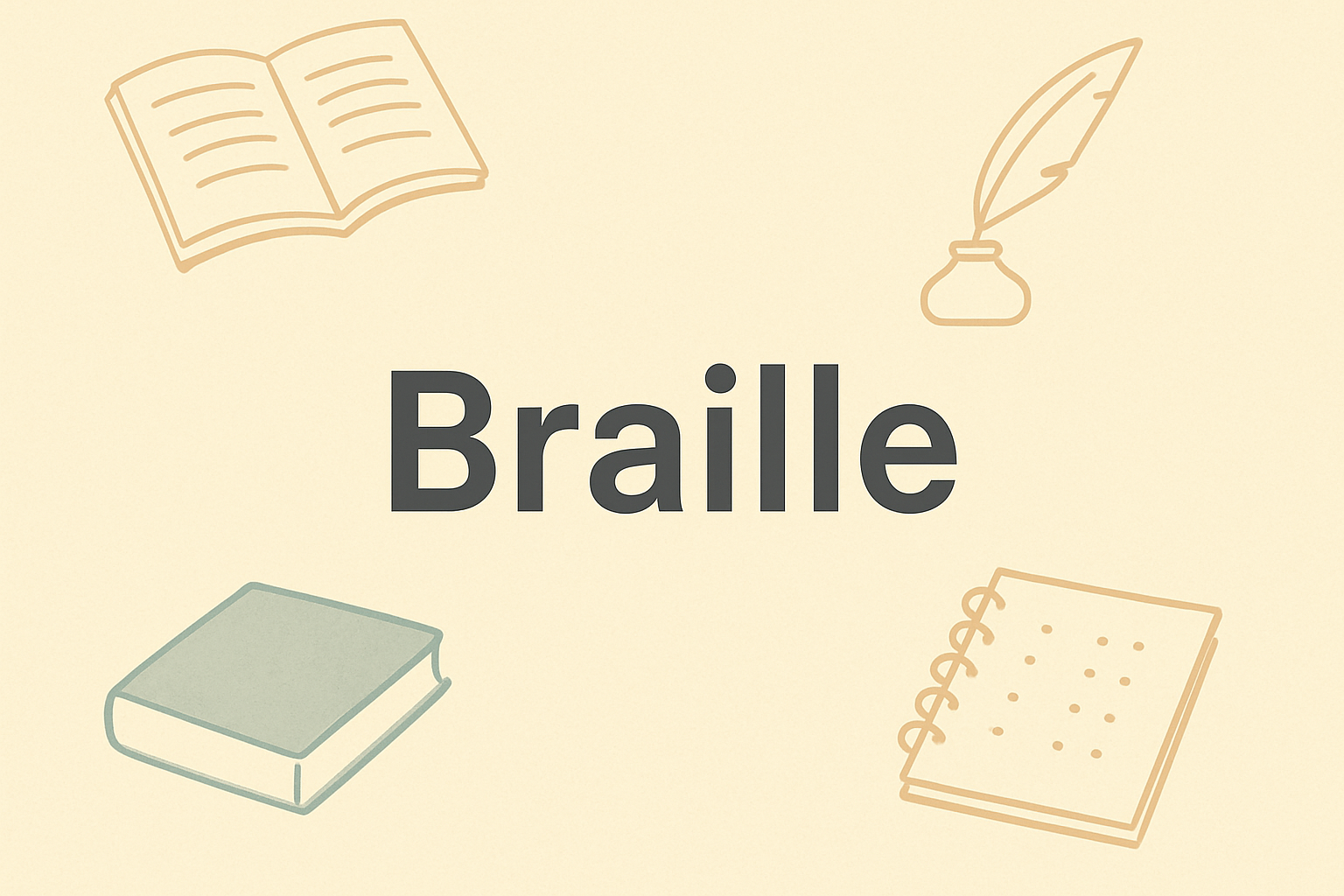ストーブがいっそう大きくのどを鳴らしているように思えた。
「鳴らしているように思えた」をどのように区切るか問題となります。
『点訳の手引き』に従えば、「いる」は補助動詞で自立語として処理するので、その前で区切らなければ間違いになります。
鳴らして|いるように|思えた。
しかし、「鳴らしているように思えた」を意味のまとまりとして区切るので逢えば、「鳴らしている」が、「鳴らして」+「いる」という「テ形」の複合動詞の意味のまとまりです。
そこで、ラボ流では、意味のまとまりや、自然なリズム、イントネーション(抑揚)を重視して、表音式で自然と考えられる箇所で区切ります。
鳴らしている|ように|思えた。
「ように」は『点役の手引き』『学校文法』『国語辞書』においては「助動詞」ですので、文節分ち書きでは付属語として前の語と続けなければなりません。
しかし、一部の学説では「ように」の「よう」は、形式名詞として扱われているので、それを根拠に区切ることを許容しています。
これによって長い文節も、一つの意味のまとまりを持った複合同士の内部で区切ることがなくなり、自然な区切りとなります。
『点訳の手引き』において、「形式名詞」も「補助動詞」も、それそれ「名詞」「動詞」なので、一律に自立語としてその前で区切ると規定するのは、不自然な区切りとなる場合があり、読み手に負担を強いると思うのです。
点字図書館は何のために、点字図書を「不自然に同質化」したがるのか疑問です。
盲学校で「学校文法」徹底したいのか?ぶつ切りにして点字用紙を節約したいのか?
日本語の英語教育で「英会話」ではなく「英語文法」から入る教育方法と似たところがあるのかもしれません、
しかし、点字は「表音式」という根源的な性格を見落としている気がします。