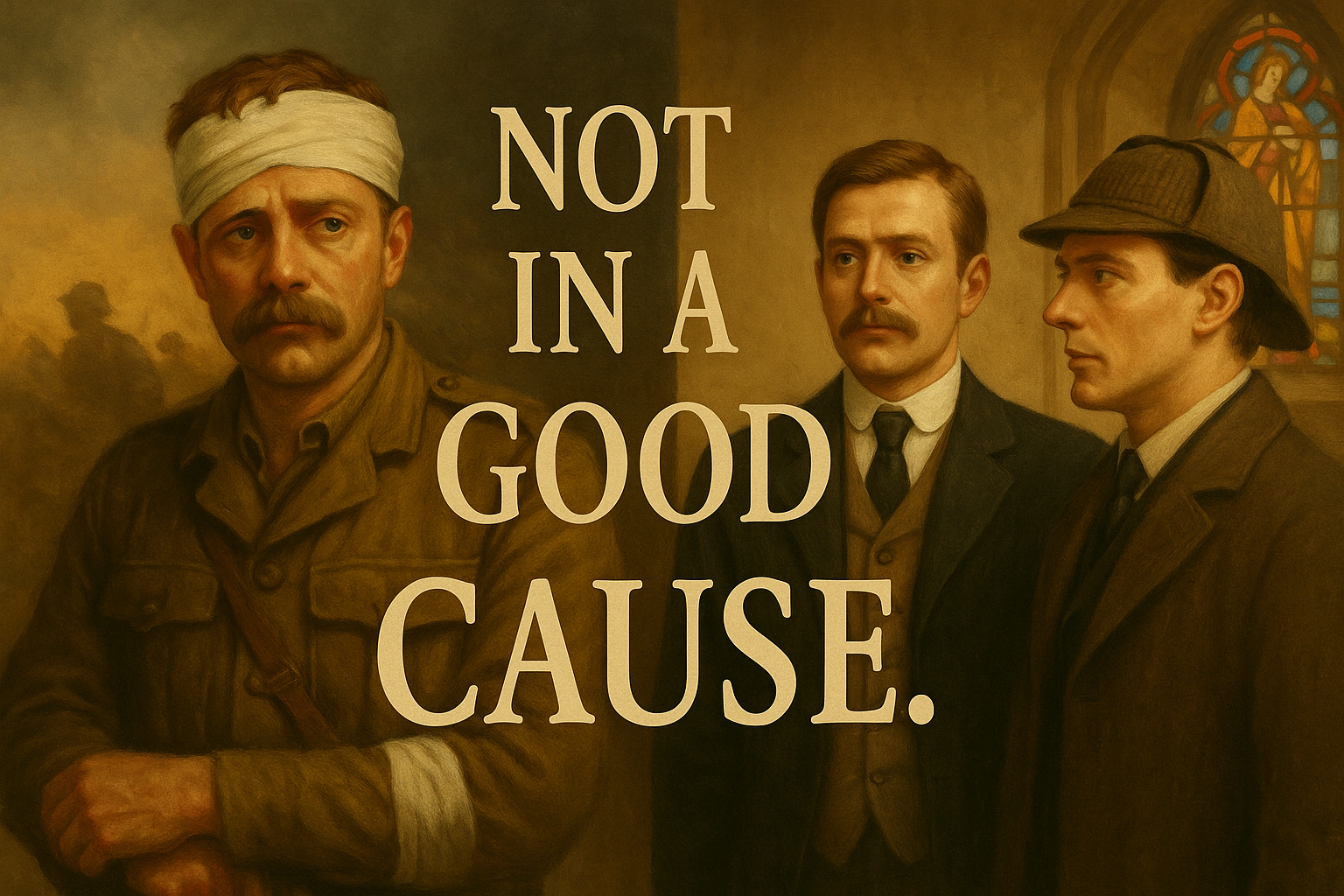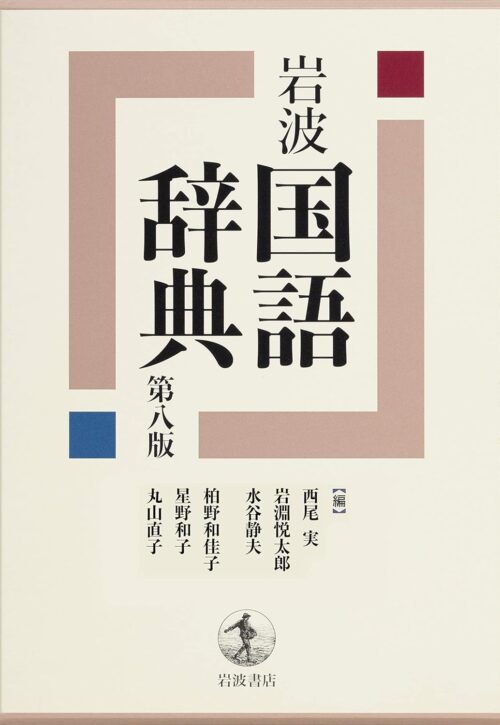「句」と「節」
「句」と「節」の違いは、述語を含むかどうかである
節(せつ)
- 定義
- 述語(動詞・形容詞・助動詞など)を含む文の単位。
- 例
- 「雨が降る」
- 「彼が来たら」
- 「本を読むとき」
- 特徴:
- 文の中で「主語+述語」という構造を持つ。
- 独立して一つの文になることも多い。
- 上位の文に含まれて複文をつくることがある(従属節・主節)。
句(く)
まとめ
| 単位 | 述語 | 独立性 | 自立語 | 例 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 必ず含む(主語+述語) | なる | 必ず含む | 「雨が|降る」 | 完全な意味を持つ最も大きな言語単位 |
| 節 | 必ず含む | なる場合がある | 必ず含む | 「雨が|降る|とき」「彼が|来たら」 | 文の中で自然な主語+述語をもつ最小単位 |
| 連語 | 含む場合と含まない場合もある | ならない | 含む場合と含まない場合もある | 「そう|して」「〜て|しまう」「では|ない」 | 決まった形で複数の語が結びついた言い回し・慣用句 |
| 句 | 含まない | ならない | 必ず含む | 「青い|空」「駅の|前で」 | 文の中で修飾や名詞・副詞的働きをするまとまり |
| 文節 | 含まない | ならない | 1語含む(複合語は複数) | 「青い」「空」「雨が」「降る」 | 文を、意味もつ最小単位に区切ったまとまり |
ポイント
- 「節」= 述語のある小さな文
- 「複文」や「重文」を分析するとき、「節」同士の関係(並列・従属)を見る。
- 「句」= 述語のない単位
- 「句」は「文節」より大きく「節」より小さい単位で、文の中で部品として使われる。
- 「連語」=意味的に強く結びついており、バラすと意味やニュアンスが変わる語の単位
- 述語を含むことがあり、慣用句・成句・文型の一部として扱われることが多い。
- 「文節」は、主に発音や意味の切れ目で分けられ、必ず助詞や活用語の区切りで切られる。
- 自立語1語を含んで構成されることが多いが、自立語を複数含んだ複合語や、慣用句は2文節を1文節とすることがある。
- 「文」=述語のある大きな単位