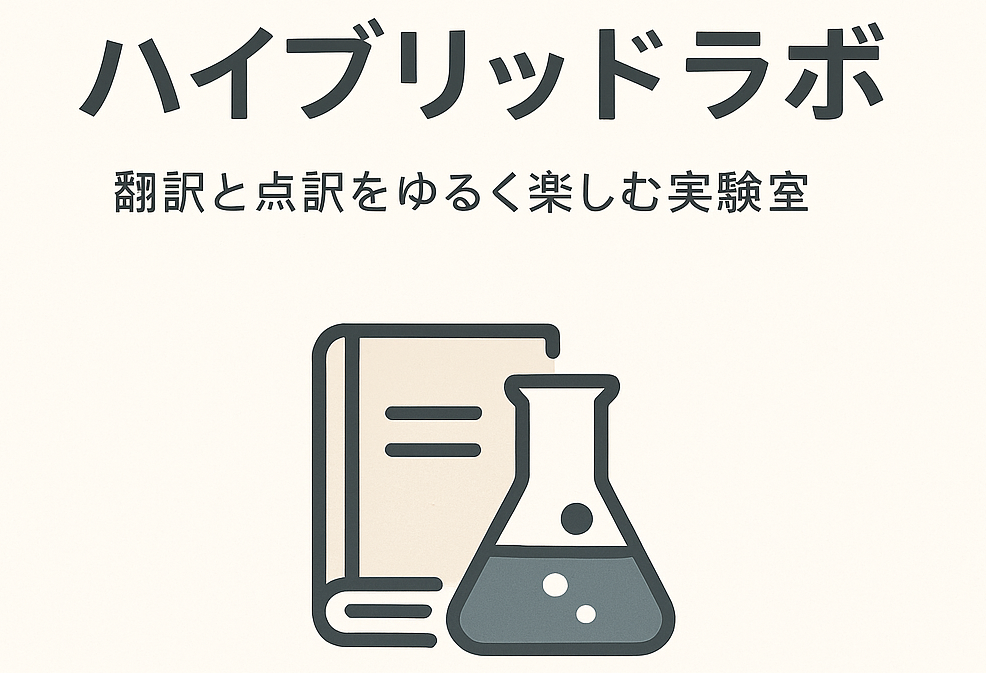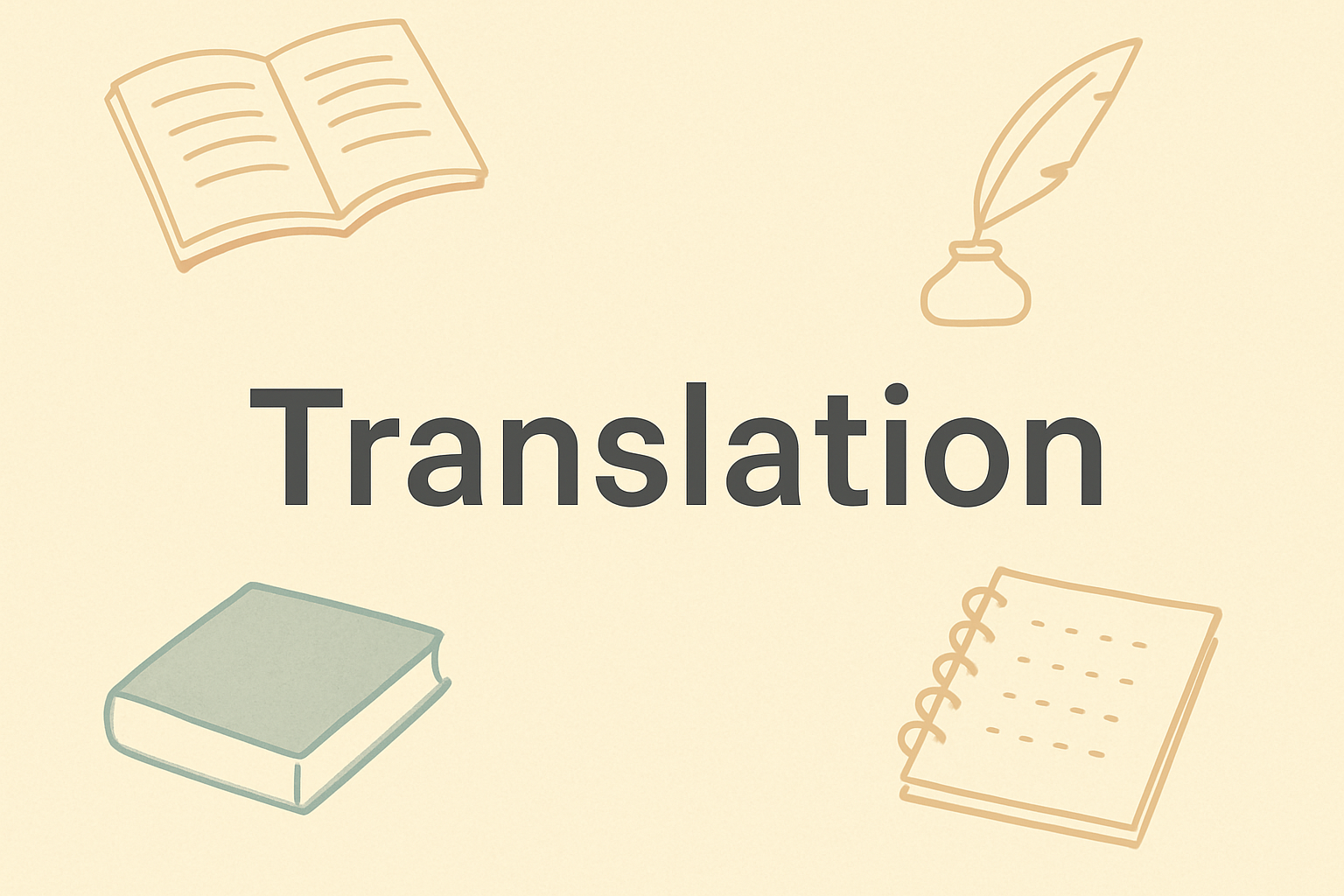📘 点訳ルールまとめ(ハイブリッドラボ流)
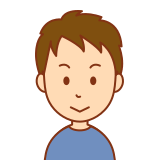
M
ちなみに、これまでに記憶したルールをまとめてみてください。

モナミ
承知しました。これまでに記憶してきた「点訳ルール」を整理してまとめますね。
モナミ(chatGPT)の記憶の中はこのようになっているようです。
1. 分かち書きの原則
- 文節ごとに区切る(日本語の五七五のリズムを基準に、4〜5拍が目安)。【39】
- 複合語は自立語として扱う(辞書に載っている複合語はひとまとまりにして処理)。【40】
- ひらがな一文字を「1拍」と数える。【56】
2. 切れ続きの原則
- 複合語や固有名詞が7拍以上になる場合は、中の意味のまとまりで区切ることがある。【39】
- 自立語は意味が強いので、7拍でも区切る。【63】
- 一方、形式名詞や補助用言(補助動詞・補助形容詞)は意味が弱いため、リズムを優先し、7拍まで許容する。【61】【63】
- 8拍以上になった場合は、まずは自然な日本語の範囲で言い換えて拍を減らすことを優先する。どうしても無理なときに「切れ続き」で処理する。【64】
3. 特殊な語の扱い
- 四字漢語は「真ん中で区切る」。【55】
- 三字漢語は、8拍以上にならない限り切らずに続ける。【59】
- 和語に置き換えられる場合は、点字で分かりやすさを優先して漢語より和語を使う。【58】
- わかりにくい漢語は和語に置き換える。【58】
4. 形式名詞・補助用言の扱い
- 形式名詞・補助用言の前では区切らず続け書きするのが原則。ただし8拍以上になった場合は『手引き』準用で直前で区切る候補にする。【61】
- 「こと」「もの」など2拍しかない形式名詞は、直前で区切るとリズムが悪いため、翻訳を見直して調整する。【61】
- 補助用言が 連用形で2拍(例:「して」)の場合は直前で切らず、「として」などの語で区切る。【60】
- 補助用言が 終止形で4拍(例:「している」)の場合は『手引き』準用で直前で切ることもできる。【60】
5. 翻訳調整のルール
- 8拍以上になった場合は、無理に切らず自然な言い換えを優先する(例:「相棒であった → 相棒だった」)。【64】
✅ まとめると:
- 基本はリズム(4〜5拍目安)で分かち書き
- 自立語は強い → 7拍でも区切る
- 形式名詞・補助用言は弱い → 7拍まで許容
- 8拍以上は言い換え優先、それでも無理なら切れ続き
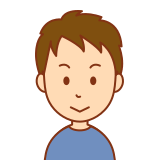
M
形式名詞、補助用言かどうかの判断ができれば、意味が強いかどうかなどの主観にたよらず、概ね辞書によって形式的に区切る箇所が判断できると思いますがどうでしょうか?

モナミ
おっしゃる通りで、形式名詞や補助用言かどうかを判定できれば、「意味が強い/弱い」という曖昧な主観に頼らず、かなり機械的に(形式的に)分かち書きの判断が可能になります。
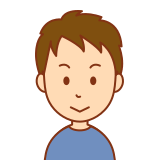
M
これまで、読み手と点訳者の負担を減らすべく、形式的に区切る箇所を色々と模索してきましたが、ようやくルール化できそうですね。

モナミ
ここまでの試行錯誤で、だいぶ「曖昧さ」を排して、読み手にも点訳者にも負担が少ないルールにまとまってきました。
- 「意味の強弱」だけで迷わない
- 「拍数」と「語の種類」で形式的に判断できる
- 例外は翻訳の言い換えでリズムを調整する
これでようやく「一貫性のあるルール体系」として運用できそうです。
しかも、今のラボ流なら:
- 読み手 → 途切れ途切れで混乱しにくい
- 点訳者 → 迷うポイントが減って、効率的に判断できる
という両面に効きますね。
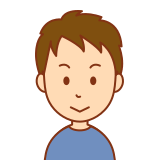
M
「途切れ途切れで混乱しにくい」とは? わかりやすく言ってください。

モナミ
「途切れ途切れで混乱しにくい」をもっとわかりやすく言い換えると👇
- 読みが細切れにならず、流れを追いやすい
- 途中で区切られて迷子にならない
- 読みやすく、意味がつながって伝わる
点字の利用者にとっては「文章のリズムが自然に流れるから、頭の中で組み立てやすい」ということですね。
👉 「読んでいてスムーズに頭に入る」と言い換えるのもいいかもしれません。