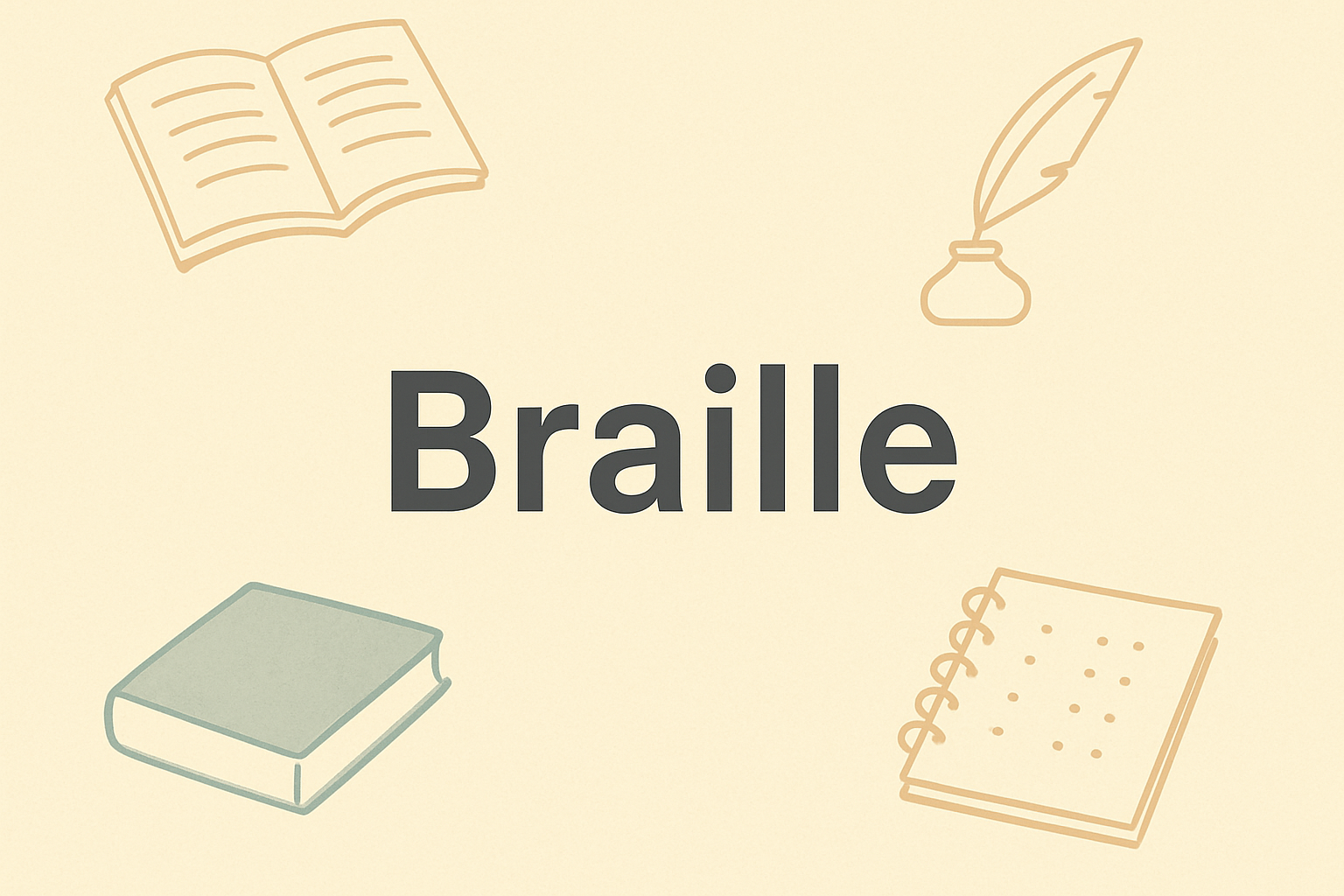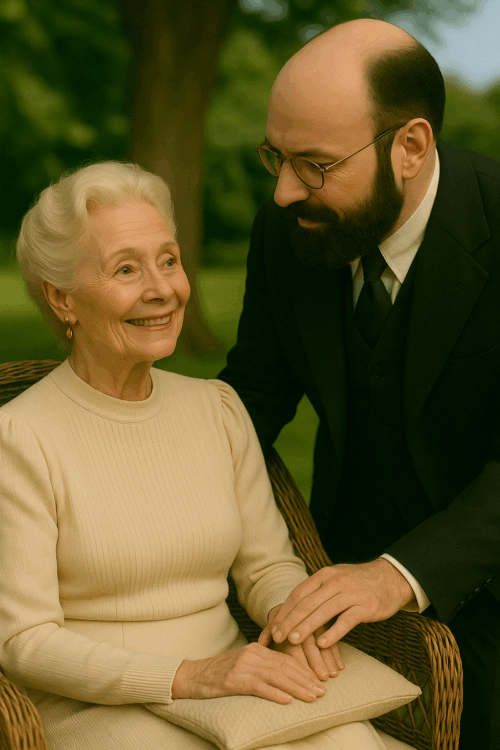先日書いた記事、読み手不在の点訳 ― 実例編4の続きです。
ライトハウス——その後
結局、ライトハウスの点訳講習は、案内文を読んで「これは自分のやりたい方向とは違う」と感じ、辞退することにしました。
ただ、お詫びのメールを送った際に、ダメもとで「視覚障害の方に読んでいただき、感想を伺う機会はありませんか」と尋ねてみました。
すると、事務の担当の方からは「ぜひ協力させてほしい、点訳担当と相談してご連絡します」との返事。思いがけず前向きな反応に、少し期待が膨らみました。
ところが、その後、(おそらく)点訳の講師の方から「自分が見るから、こちらに来てほしい」との連絡。その方は「あの人の講習もただ『手引き』を読むだけだよ」と以前から名前を耳にしたことのある方で、嫌な予感がしました。
そこで不毛な議論したくないと思い、ライトハウスに伺う前に、とりあえず『赤毛連盟』のBESファイルを送ってみることにしました。
点訳講師の方からの返信
ほどなくして、点訳講師の方から、たいへん丁寧な返信が届きました。
しかし、その内容の大半は「日本点字表記法2018」がいかに権威あるルールであり、それに基づく『点訳の手引き』がいかに信頼すべき規範であるか——という説明に費やされていました。
いかにも「手引きこそ聖典」という語り口で、どこかで見たことのある『まえがき』か『編集後記』を読んでいるような気分になる内容です。
言わんとするところは要するに、
- 公的に出す点字は必ずルールに従うべき
- 個人的に書く分には工夫もありうる
- 今回のデータも「自然な区切り」で、個人の試みとしては理解できる
という実に規則重視で上から目線のお答えでした。
この一言こそ、公にしていいのか?
ただ、「不特定多数、公に出す点字は、このルールに沿っていることが求められます」「ただ、不特定の方が読むもの、公にするものなら日本点字表記法に沿って書いてください、となるかと思います」という指摘がありました。
この言い方は、「社会福祉法人」として、それこそ「公式」に活動されてる職員の「個人の表現の自由に対する姿勢」としていかがなものか?という疑問は残りました。
古い話かもしれませんが、「発表するなら規則を守れ」的な物言いは個人間ならまだしも、公的法人の職員が使うと「検閲的」に響くのです。
もちろん、この言葉は、憲法21条が禁じる「検閲」とは異なり、法的な意味での拘束力を持つものではありません。
しかし実際には、私の活動に対して「これ以上は公開してはいけないのではないか」と感じさせるほどの萎縮効果(chilling effect)を生みました。
「不特定多数」「公にする」という言葉は、法令や判例においては強い意味を伴う用語です。
そうした言葉を、社会福祉法人という公的な立場を持つ職員が用いたとき、それは単なる個人意見にとどまらず、個人の表現の自由に対して検閲的な圧力として作用し得るのではないでしょうか。
先日、点字図書室で言われた「手引きに準拠していないものは点字図書室に置けないんです」と言われたときとはちょっとが意味合いが異なります。これは単なる「施設の蔵書方針に基づいた判断」にすぎません。
ちなみにこの時は、置いて欲しいなんてことは一言も言ってなかったので、「著作権は私が持っているのだからタダじゃ置かせないよ」と答えました(笑。
本来あるべき言い方
どうせ書きたいのなら、例えばこうなら私の不快感はぐっと減ったはずです。
- 「サピエ図書館に寄贈して広く流通させる場合には、日本点字表記法に準拠する必要があります」
- 「一方で、研究や個人の公開活動としての工夫も大変興味深く、今後の参考になります」
こう書けば、「制度上の公式」と「社会的な公開」の両立を認める形になり、公的な立場での意見として認容できるわけです。
『点訳の手引き』は不自然なのか?
もちろん、「自然な区切り」という一言はいただけました。これは素直にありがたかったです。
逆に言えば『点役の手引き』の分かち書きは「不自然」ということを言っているのと同じだからです。
ただ、このwebサイトは当然見ておられないでしょうから「初心者が適当に区切っただけ」というのが本心でしょう。
また、私が本当に求めていた「視覚障害の方に触読していただき、感想を伺う機会」については、完全にスルーされていました。
邪推ですが、規則に沿わない点訳資料を視覚障害者の手に触れさせることによって、これまで従ってきたルールに批判的になったり疑問を持って欲しくないという判断かもしれません。
そしてそれこそが、社会福祉法人「ライトハウス」の職員のいう「公にする」=「不特定多数の人の目に触れさせる」ということなのかもしれません。
感想
返信を読み終えて、やはり「予想通りだった」というのが正直な感想です。
残念ではありますが、最初から覚悟していたことでもあり、一方でホッとした面もあります。
ただ、まさか「不特定多数」や「公にする」と言った法的に重く感じる言葉が、こうも軽々しくメールの中で使われたのは、まさに「斜め上から」攻撃されたようで予想外でした。
ただ、「自然な区切り」という感想はいただきました。これは『点訳の手引き』に対する事実上の収穫であり、ラボ流の方向性がまったく見当違いではないという確認になりました。
けれども、私が「ハイブリッドラボ」の活動を進めていく上で、本当に知りたかった「視覚障害の方がどう触読し、どう感じるか」という声には、今回もたどり着けませんでした。
結局、公的な場では「手引き」という「権威」が優先され、読み手の実感は置き去りにされる——その現実をあらためて突きつけられたわけです。
これからは・・・・
しかし、だからこそ私は確信しました。
実例編2 で宣言した「制度に縛られない趣味の点訳だからこそ、その自由と責任でやっていく」との立場です。
閉鎖性を打破しようとして、点訳の新しい基準を積極的に示す必要はない。
実際に「サピエ図書館に寄贈するためだけ」に、日々点訳にご苦労されている方々を説得するつもりはないし、そのために自分の貴重な時間を費やすつもりもない。
私は私の場所で、自由に点訳活動を行い、自由にvia lexica のサイトで作品を公開していけばいい。
その中での自分の体験は、批判的に、そしてユーモラスに「駄文」として書き残していけばいい。
そうした記録が、いつか誰かにとって「当時の証言」となるかもしれないのだから。
未来を見据えた駄文
「駄文置き場」は「研究ノート」ではなく、新しい知見や成果があるわけではありません。
けれども、ここに書き残すことは無意味ではないと思っています。
20年先、もしかしたら点訳界が変わっているかもしれませんし、変わっていないかもしれません。
そのとき、この記事が「当時はこうだった」という証言になれば、それで十分です。
だから私はこれからも、「異端派」として、点訳活動を続けていこうと思います。
余談)公にするなと言われたので、逆にこうして公にしてみました。