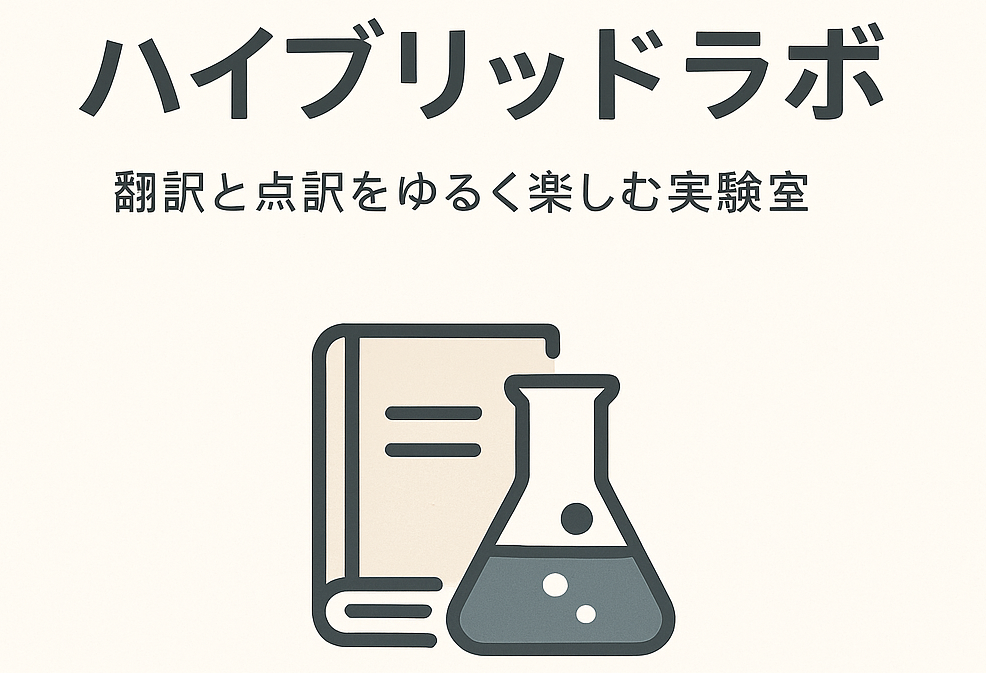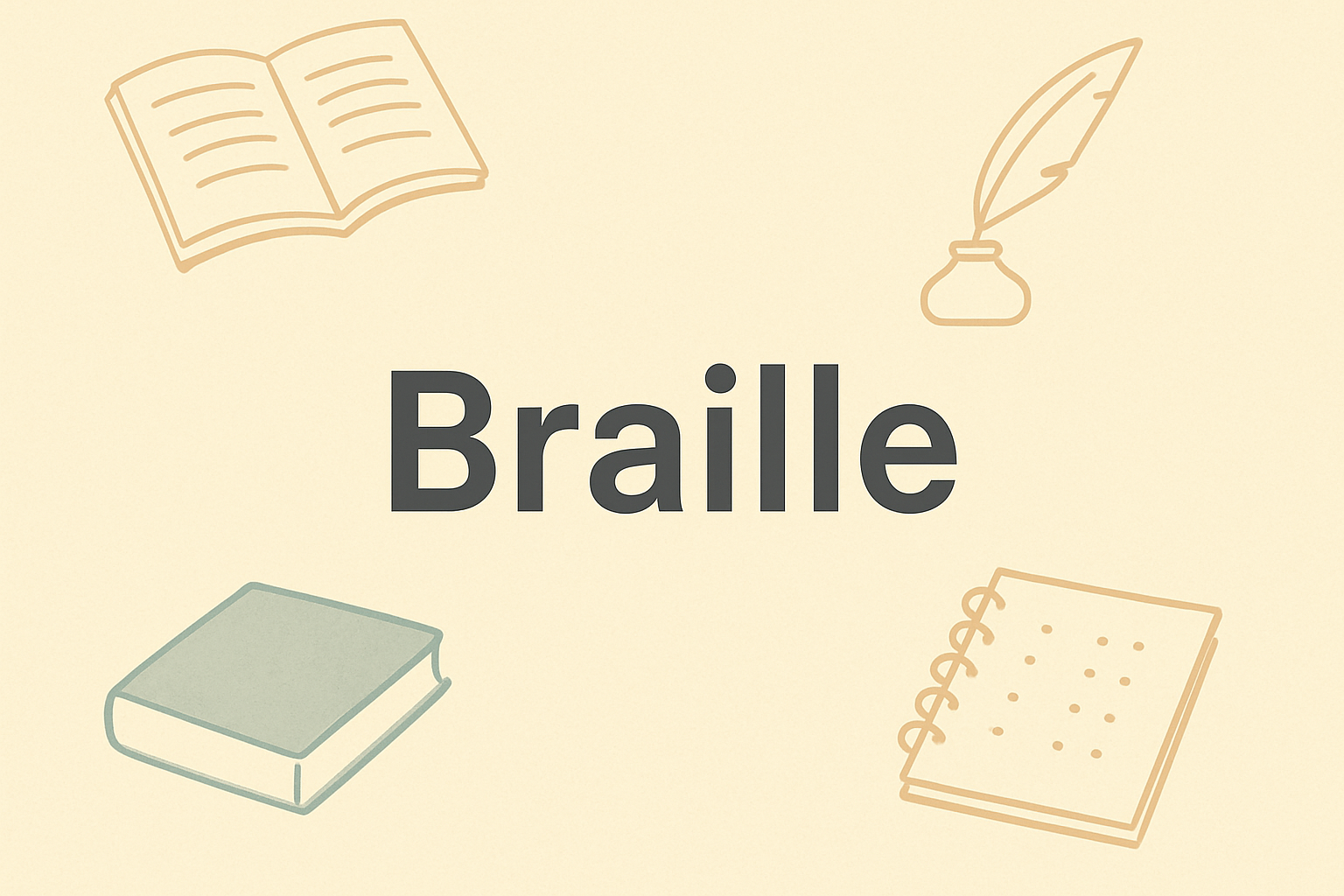ハイブリッドラボでは翻訳と点訳を並行した同時作業として翻訳しています。
市販の文庫本は、翻訳者も点字にすることまで意識して翻訳してないと考えるのは自然だと多います。
しかし、翻訳と点訳を同時にやると、ちょっとした翻訳の工夫で、点字にした場合の読みやすさが、格段に向上すると思います。
スタイルズ荘の怪事件の一節です。

“Well, of course the war has turned the hundreds into thousands. No doubt the fellow was very useful to her.
「まあ、|戦争の|せいで、|その|<幾つもの>数が|何倍にも|増えたわけだ。||だから、|この男は|母さんに|とって|とても|役に立ったのは|間違いない。
ここに出てくる「役に立ったのは」は、8拍ありますので、ラボ流の7拍基準では、切れ続きの対象となります。
しかし、どこで区切るべきか?
『点訳の手引き』に従えば、「役に」(名詞+助詞)、「立ったのは」(動詞+助詞)で、「役に|立ったのは」とすべきでしょう。
しかし、「役に立つ」が一つの慣用語(複合動詞)として、辞書に掲載されてます。
役に立・つ|その目的に有効に働く。(明鏡)
役に立・つ|使って効果がある。有用である。(大辞泉)
役に立・つ|その役目を果たすのに適している。その役割を十分に行う能力がある。役立つ。(スーパー大辞林)
とすると、「役に|立ったのは」と区切るのは、できれば避けたいのです。
ではどうするか?
自立語が二つあるけど、このまま「8拍で我慢」してもらうという選択もあります。
しかしラボ流では、7拍基準にあっては、出来うる限り妥協はしたくないのです。
そこで、同じ意味を持つように表現を工夫することで、すっきり解決します。
だから、|この男は|母さんに|とって|とても|役に立った|ことは|間違いない。
「役に立ったのは」(8拍)を、敢えての9拍にして、「役に立った|ことは」というように「6+3」という「3拍以上7拍以下」のリズムの良い拍数にするのです。
「ことは」は形式名詞ですので、ラボ流では7拍以下のときは「続け書き」ですが、8泊以上になれば、その前で区切ることを許容します。(第3層|切れ続きする箇所の手がかり💁♂️)
この場合の「のは」の「の」が、「形式名詞」という言語学上の説もあリます、
とすれば、「役に立つ|のは」と切れ続きすることも文法上は可能ですが、ラボ流は、文法的判断は「どっちだっていい」という立場です。
読み手目線では、「の」の前で区切っても「のは」という2拍の意味の弱い文節を作るだけで、意味の理解を助けることにはならないと考え、この切れ続きは採用しません。
このように、ハイブリッドラボでは、翻訳段階から点字にすることを意識して文章を考えているので、点字の読み手にとって読みやすくなるものと信じています。
「Agatha Christie, The Mysterious Affair at Styles (1920) より引用」