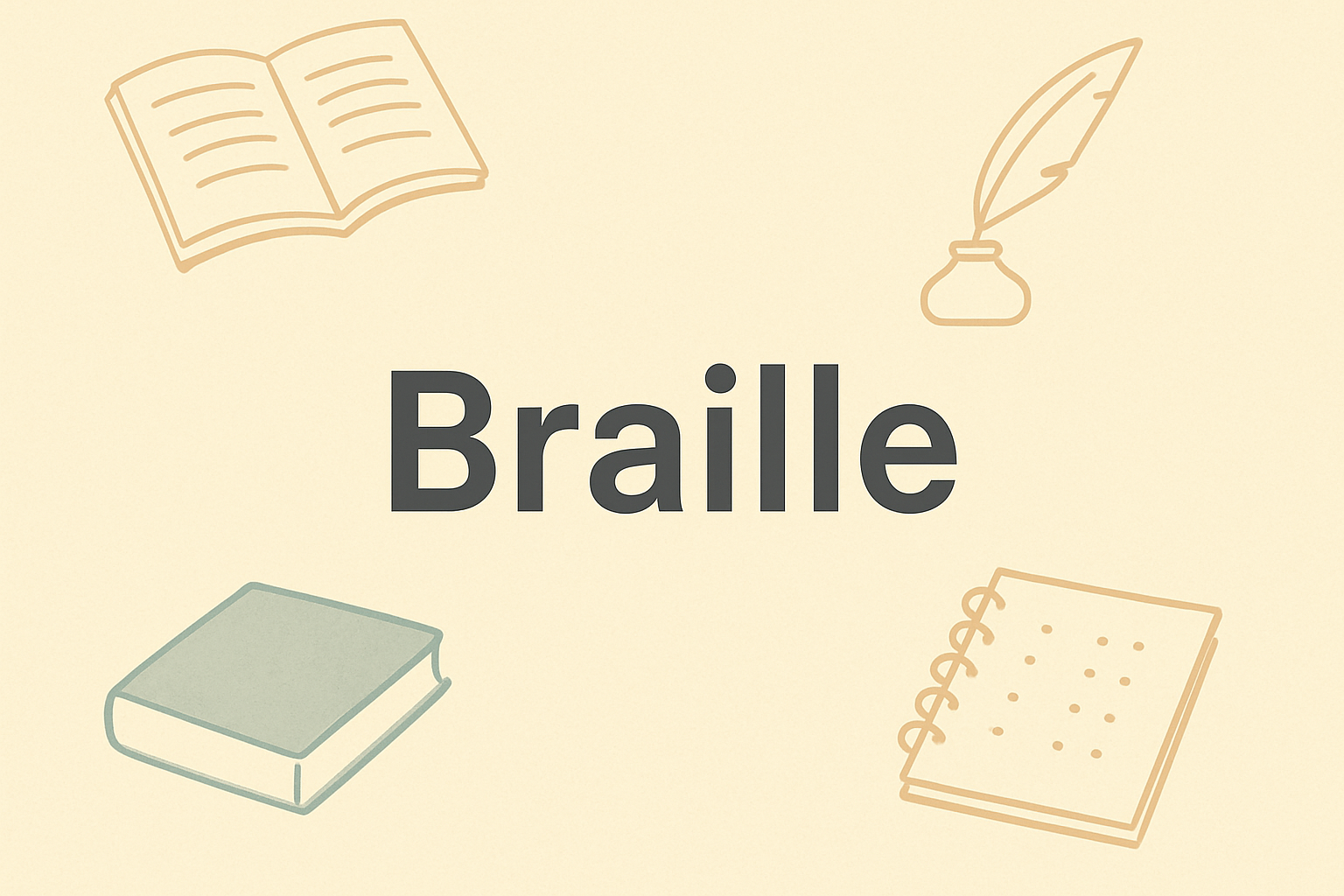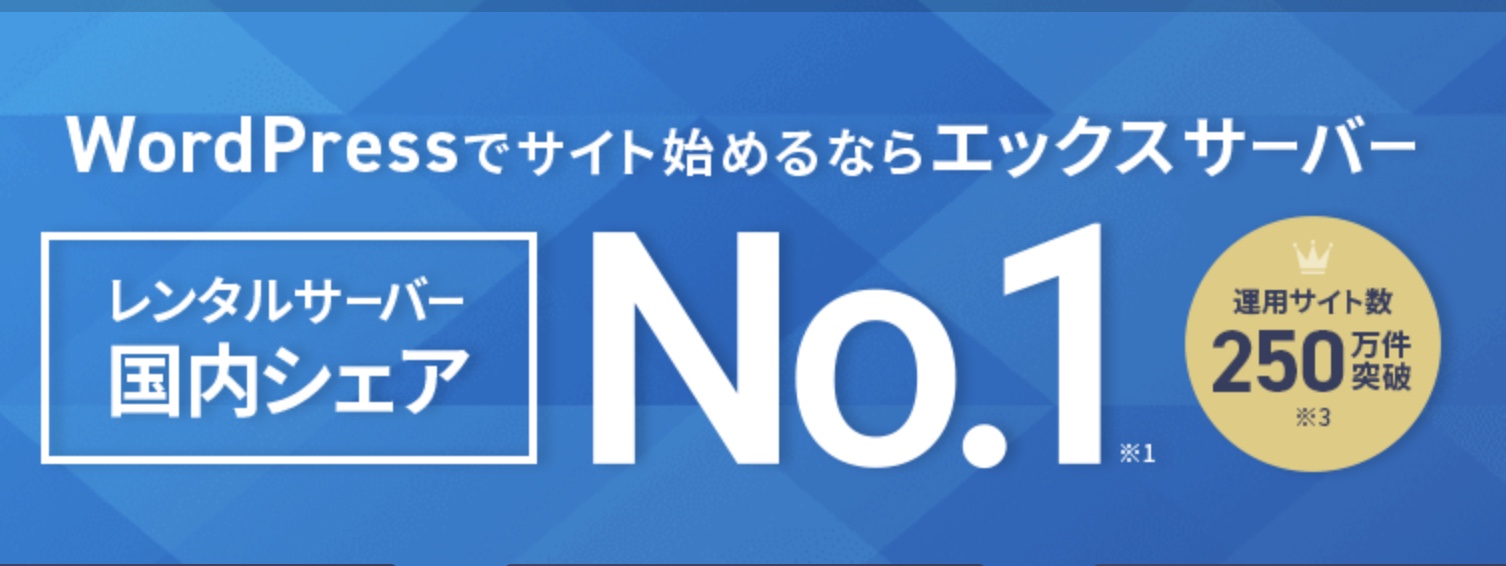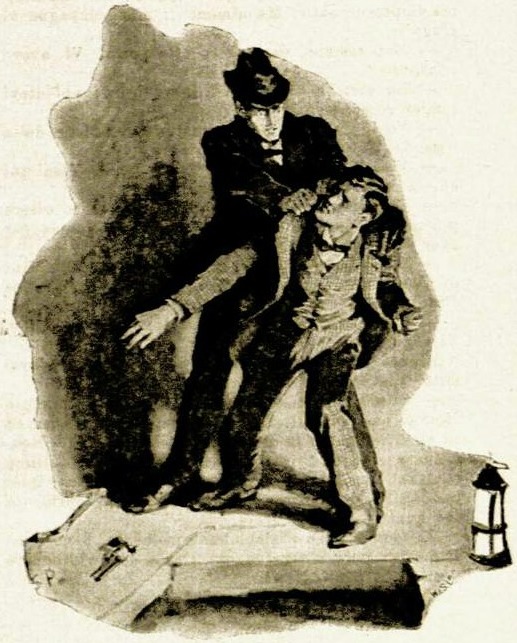点訳の手引きには、「楽しみに|して|いる」といった具合に、品詞ごとに細かく区切るような指示が見られます。公式の理由は「意味の明確化」「誤読防止」。
確かに文法的に見れば、「して」は動詞「する」の連用形、「いる」は補助動詞。どちらも「動詞」である以上、別々に扱うのは理屈として正しい。つまり「して|いる」と切るのは、文法的な根拠に裏打ちされた処理です。
でも実際に点訳をしていると、「なぜそこまでぶつ切りを徹底するのか?」と首をかしげたくなることがあります。
行移しの効率と紙の節約?
「楽しみにしている」を例に考えます。
- 「して|いる」を、続け書きで「している」とした場合、行末にかかると「している」全部を次の行に送らねばなりません。前の行には空マスが残り、紙の無駄になります。
- 一方「して|いる」と切れば、「して」で行末を埋め、「いる」だけを次の行に送れる。行のマスをぎりぎりまで使えて、紙を節約できます。
『日本点字表記法』で「して」も「いる」も『自立語』として扱った結果ですが、本当に「自立した言葉」と受けとめられますか?
行末の空白が長いと「読み手が迷う」という意見もありますが、「して」という2マス程度の行末の空きは普通に存在します。
昔の点字現場では「紙を積んできた船が沈没し、塩水に浸かった紙までもが貴重だった」という話すらあります。そう思えば、手引きのぶつ切りは文法的な正しさだけでなく、用紙を大事に使うための工夫でもあったのかもしれません。
シュークリームの悲劇
似たようなことは「シュークリーム」でもありました。規則に従えば「シュー|クリーム」と切れ続きにできます。説明では「フランス語でシューはキャベツで、クリームはクリームで…」ともっともらしい根拠が並ぶのですが、講習に来ていた視覚障害者の方はこう言いました。
「行末で『シュー』だけ残って、『クリーム』が次の行に行くのは勘弁してほしい」
言われてみればその通り。日本語では完全に「シュークリーム=お菓子」の一語ですし、行の途中で分断されれば読みづらい。ここでも「規則より読みやすさ」が勝つのだと実感しました。
SMAPとKAT-TUNの混乱
さらに講習では、ジャニーズの話まで飛び出しました。
「SMAPは略語だから S.M.A.P. とピリオドを入れるのが正しい」と某講師が真顔で言うのです。すると誰かが聞きました。
「じゃあ KAT-TUN はどうするんです?」
一同大爆笑。「だいぶ減りましたねえ〜」で話は終わり、もう何が何だか…。
そもそも、SMAPを略語だからと敢えてピリオドを打って、読み手に伝える意味はあるのでしょうか?
というか、私が調べた範囲では商標登録は「SMAP」です(´∀`)
ラボ流の整理
こうした実例を振り返ると、ラボ流としては次のように「5・7・5」のリズムを基準に「3段階基準」で考えるのがしっくりきます。(詳しくはこちら💁♂️)
「3段階基準」
- 5拍以下
- 文節の標準拍数(3〜5拍)で、原則、続け書きする。
- 6〜7拍
- 原則、続け書き
- 8拍以上
- 原則、区切って書く
文法の位置付け
ラボ流では、拍数が多すぎたり、リズムが崩れる場合に「どこで切るか」を考える。そのときに初めて文法(品詞の切れ目)が登場します。
つまり「文法は常に最初から優先するルール」ではなく、リズムを助けるための補助線にすぎないのです。
追記)品詞の切れ目で区切り方法に加えて、イントネーション(話すときの自然な抑揚)の変化点で区切る補助原則も考えています。詳しくはこちら💁♂️
結局のところ
- 手引きの「ぶつ切り」は、文法的な正しさと、当時の点字用紙不足という事情の両方に支えられていた。
- でも現代ではデジタル化が進んだことで紙の制約はなくなり、触読のリズムや読みやすさを優先できる。
- シュークリームやSMAPの例を見ればわかる通り、規則の理屈より「読んでわかる」ことの方が大事。
こうして考えると、点訳の歴史もなかなかユーモラスに見えてきます。もし自分が昔の「紙を節約せよ」と叱られる時代に生まれていたら、きっと無理やり文法をこじつけてでも立派な「ぶつ切り推奨派」になっていたでしょう。
でも現代の自分は、シュークリームをキャベツ扱いせず、SMAPを略語表記せず、リズムと読みやすさを大事にしていきたい——そんなふうに思う今日この頃です。