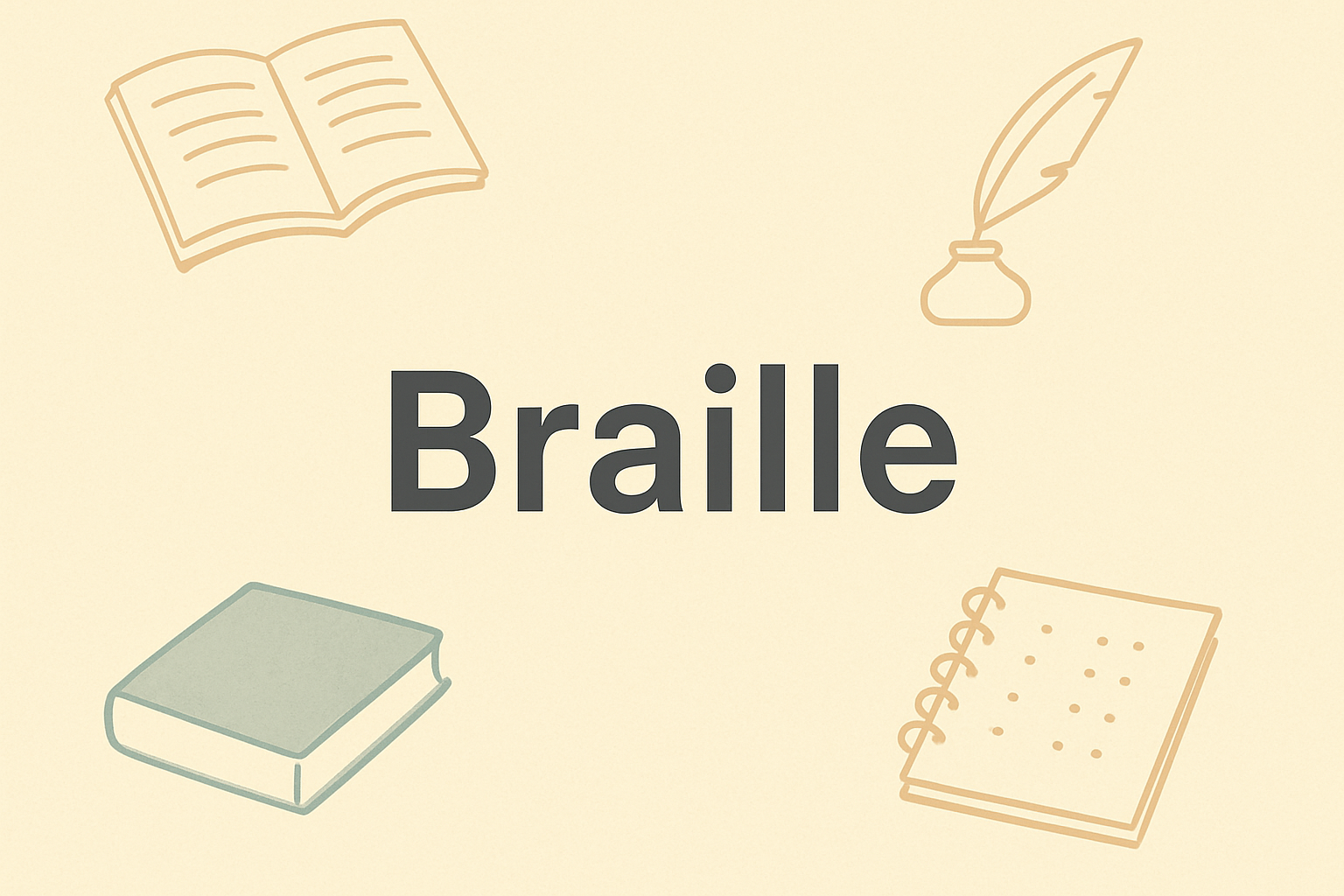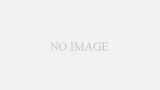「ライトハウスの案内文」をきっかけに、ラボ流との違いを浮かび上がらせる
― 案内文を読んで
先日、某ライトハウスから「点訳ボランティア講習」の案内文が届きました。
そこには、点字の歴史や「辞書で調べて正しく仮名に置き換える忍耐力」「国語文法との格闘」といった言葉が並んでいました。
辞書と文法との格闘
案内文は、点訳作業を「誤読を避けるために辞書を引き、正しい読みを探すこと」として強調していました。
もちろん、漢字の読みを取り違えれば点訳は成り立ちません。
「日暮里」を「ひぐれさと」と誤って仮名化してしまえば、視覚障害の方にまったく別の情報を伝えてしまいます。
その意味で「正確さ」は不可欠です。
けれども、案内文で繰り返し語られていたのは「忍耐力」「工夫」「探究心」といった点訳者側の姿勢でした。
読み手が見えない文章
案内文には「視覚障害者」という言葉は出てきます。
しかしそれは「点字利用者は減っているが、点字は必要だ」といった制度的な文脈であり、
「どうすれば触読がスムーズになるか」
「どうすれば誤読せずに理解できるか」
といった読み手の感覚には触れていませんでした。
ラボ流との違い
私が考える「ラボ流」の点訳は、翻訳の段階から 「誤読させない」「読みやすい」 を最優先にするものです。
つまり、常に 視覚障害の人がどのように触読するかをイメージする。
そのうえで文のリズムや語彙の選び方を工夫します。
ところが今回の案内文に表れていたのは、点訳者側の立場でしかありませんでした。
辞書を引く姿勢、文法と格闘する忍耐力――確かに必要ではあります。
しかし、そこに「読み手の姿」が欠けている限り、私の目指す点訳とは交わりません。
残念に思うこと
点字は極めて優れたシステムであり、もっと社会に広く浸透してほしいものです。
けれども、現状の案内文を読むと、点訳は「文法との格闘」という閉じた世界にとどまっているように感じました。
私は、点字が「読む人」の文化として根づいてほしいと願っています。
そのためには、点訳者側の忍耐や制度上の統一だけではなく、触読者のリズムや感覚を中心に据えることが必要だと思います。