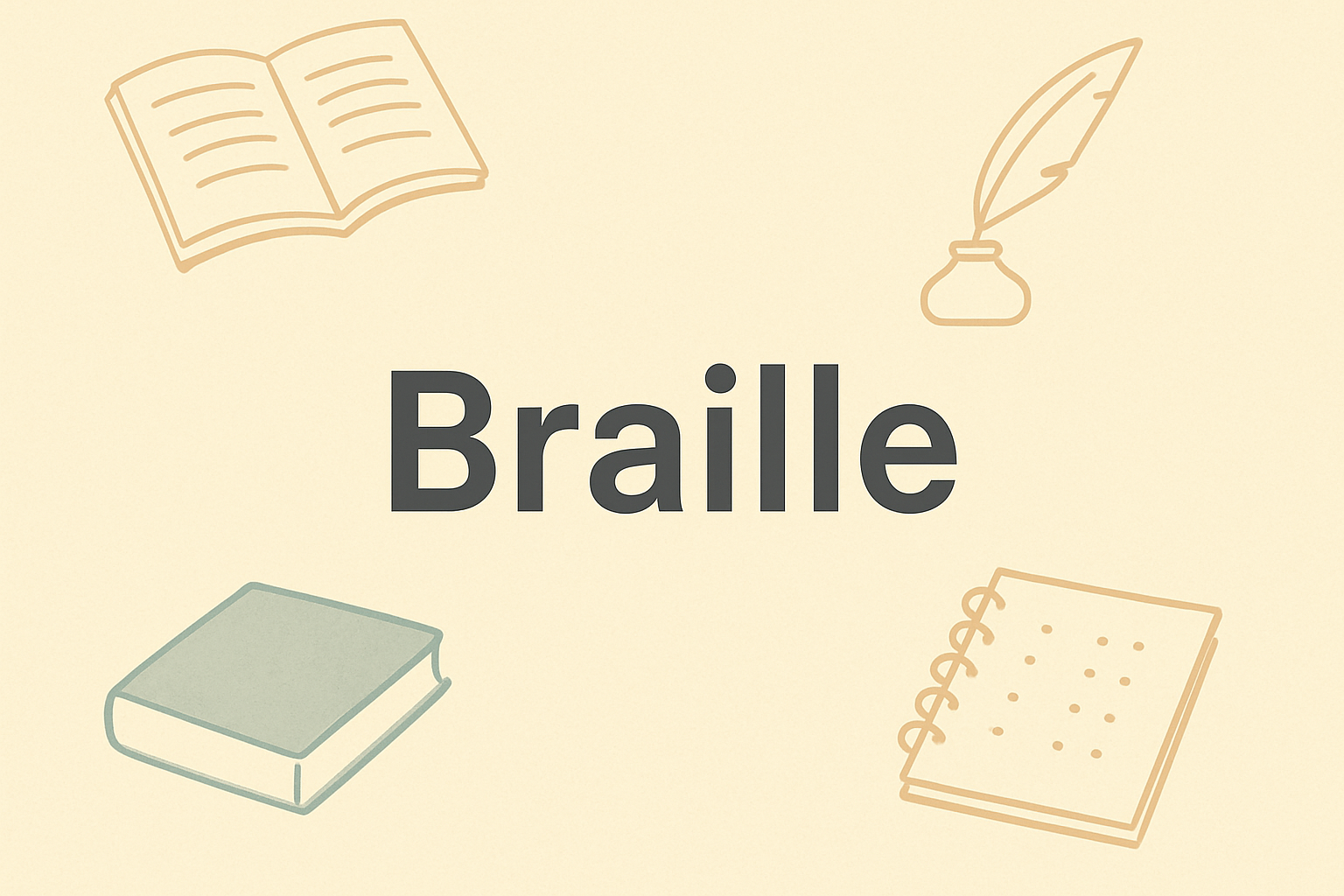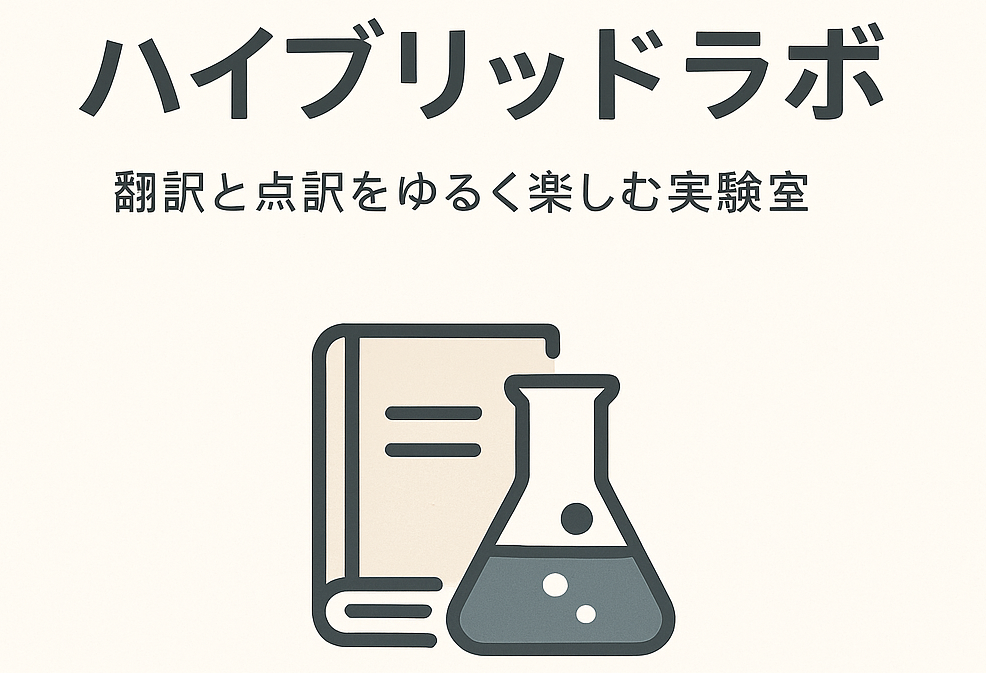点字図書室でのやりとりを通じて、改めて「読み手不在」という感覚を持ちました。
——メアリージョーの続き
前回、「メアリー・サザーランド嬢」が点訳では「メアリー|サザーランドジョー」となり、まるで別人名のように読めてしまう――という“誤読”の典型例を書いた。
今回は、その続き。現場で実際に起きた「読み手不在」をもう一件、記しておく。
ホームズの「裁判官のような」
私が訳していた一節。
ホームズは椅子にもたれ、指先を合わせた。
これは彼が裁判官のような口調で話し出すときの姿勢だった。
この「裁判官のような」を点訳するとき、私は「ような」の前で区切りたくなった。
理由は単純。10拍もあるまとまりを触読するのはリズムが悪く、視覚障害の方に負担を強いるのではと思ったからだ。
ところが「点訳の手引き」では「ような」は助動詞扱い、原則は続け書き。
展示図書室の担当の方の見解はこうだった――
『の』の後ろに助動詞が来るのはおかしいと思う。だから『よう』は形式名詞だと思う
ここで重要なのは、その方の言い方が「〜だ」という断定ではなく、根拠の示されない「〜と思う」という判断をしている点だ。
推薦された参考書と、後日談
点字図書室の方が「わかりやすい」と推薦してくださった市販の解説書
『点字・点訳の基本』(=手引きを読みやすく整理した本)を手にしている最中のことだった。
私は同書58頁に「山のような」という用例を見つけた。
そこでは、原則どおり続け書きということが明記されている。
つまり、「助詞『の』の後ろに助動詞は来ない」という説明は、この参考書と矛盾している。
私は、本の返却ついでに「参考までに」とお伝えしたが、返事はなかった。
自然な感覚が、文法論でねじ曲げられる
点字図書室の方の感性による誤解は、本当のところ「拍数」だと思う。
「山のような」は6拍で続けて読んでも苦にならない。
でも「裁判官のような」は10拍、一息で声を出して読むにしても、続けて触読するにしても読み手の負担は大きい。ここで分かち書きしたいという自然な感覚が生まれる。
ところが、点字図書室の担当者の方にように自然な感覚を正当化しようとして、根拠の薄い文法論に寄りかかると、議論はおかしくなる。
自分と同じ感覚を持つはずの「読み手」の姿がそこにはないからだ。
文法論で話をしよう。
国語辞典の多くは「ようだ=助動詞」と扱う。一方、言語学系の文法書には、「よう」+「だ」として「形式名詞+助動詞」という分析も存在する、この解釈で「手引き」則れば、形式名詞「よう」の前で区切って書くことになる——即ち、どちらも言い得るのだ。
文法的には、つまるところ・・・・
どっちだっていい!
だからこそ、最後に頼るべきは読みの実際=触読の体感だ。
「同質化」という理屈と、その副作用
「手引き」が必要だと言われる最大の理由は、サピエ図書館に収める点字図書を同質にするため——全国どこで読んでも同じ表記で迷わせない、という理屈だ。
しかし、同質化を盾に「規則の一貫性」が読みやすさを犠牲にする場面が生まれていないか。
しかもサピエでは、一度収蔵した図書は基本的に作り直さない運用だという。
表記法が改訂されても過去の規則に従った訳本はそのまま。つまり時期によって表記の仕方が違うことが起きうる。
これ、結局のところ視覚障害の方に負担を回しているのではないか。
私の結論―優先順位を取り違えない
私が点訳で最優先するのは、たった二つ。
- 誤読させないこと
- 読みやすいこと
この順番は、そのまま『日本点字表記法』の第1原則(分かち書き)、第2原則(切れ続き)の精神に通じているはずだ。
形式や同質のために、読みの実際を犠牲にしない。ここを外したら、点訳は目的を見失う。
だから私は言い切る。
「点訳の手引き」“だけ”に縛られた点訳はしない。
必要なのは、手引きを道具として使いこなし、最後に“触読の現実”で判断する姿勢だ。
私は翻訳段階から言葉を選び直し、視覚障害の方の読みに合わせて誤読を潰し、読みを軽くする。
制度に縛られない趣味の点訳だからこそ、その自由と責任でやっていく。
「メアリー嬢」問題も、「裁判官のような」問題も、読み手を最初に置けば迷わない。
これからも、この順番で続ける。