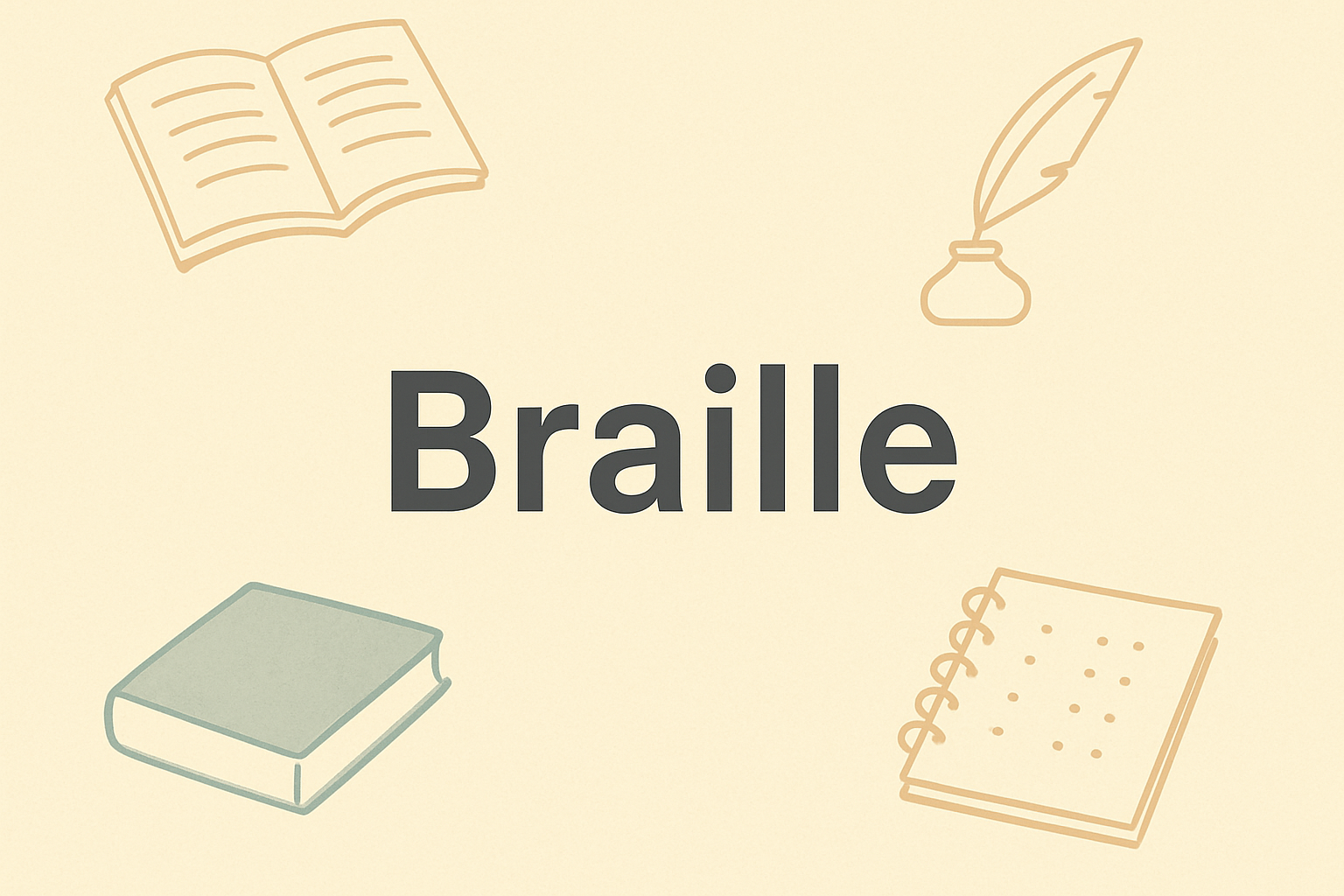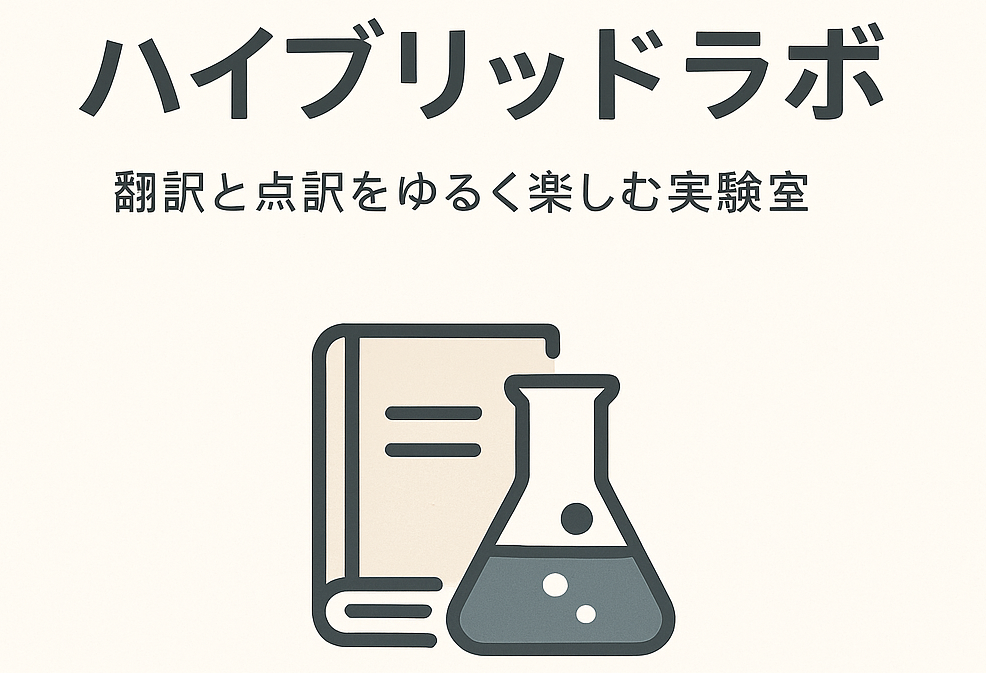前回の記事で「点訳の手引きなんていらない!」と書いた。
今回は、その理由をもっとわかりやすくするために、具体例をひとつ紹介したい。
『赤毛連盟』に出てくるメアリー嬢
ホームズの短編『赤毛連盟』の中に「メアリー・ザーランド嬢」という人物が登場する。
これを点訳すると、手引きに従ってこうなる。
めありー|さざーらんどじょー
これが「正しい」とされる点訳だ。
読み手にとっての問題
墨字の読み手なら「嬢」という字を見て、「お嬢さん」の嬢だと分かる。
しかし点字の読み手は、漢字を前提にしていない。
つまり 「嬢」という字を知らない状態で、“じょー”という音だけを手探りで読む。
ここでさらに問題がある。
原則通り「じょー」と長音符を使うと、むしろ人名の一部のように見えてしまう。
それに対して「じょう」と書けば、人名ではなく敬称であると区別しやすい。
また、「病気や事故で視覚障害を負った人は漢字を知っているじゃないか?」と思うかもしれない。
だが実際には、途中失明した人で点字を読む人は少数派である。
点字を日常的に使うのは、むしろ生まれつきの視覚障害者が多い。
だからこそ「嬢」という漢字の知識に頼った点訳は、現実の読み手には届かない。
中点の役割
さらに、この例では中点の有無も重要だ。
手引きでは、人名のなか点は、省略して「マスアケ」できる、というより「推奨」さえされる。
めありー|さざーらんどじょー
では、読み手は「名前がどこで終わるのか」を予測できない。
一方、中点があると、
めありー・|さざーらんど じょう
このように、マスあけの前に「⠐」が登場することによって「まだ名前が続く」と指先で予測できる。
中点とスペースの工夫によって、読みやすさが格段に増す。
ここに現れる溝
つまり、
- 手引きどおり → 文法的には正しいが、誤読や混乱を招く
- 読み手に寄り添う → “じょう”と書き分け、中点や区切りを加えることで、人名の理解がスムーズになる
墨字は漢字という“形”に意味を託すが、点字は表音文字であり、“形”ではなく“音”で伝える文字だ。
だからこそ点訳は、漢字の知識に頼るのではなく、指先で音を正確にたどれることを第一にすべきなのだ。
翻訳の段階から
なお、私の「翻訳+点訳プロジェクト」では、翻訳の段階から工夫している。
「メアリー・ザーランド嬢」ではなく、英語原文どおりに
「ミス・メアリー・サザーランド」
と訳出しているのだ。
こうすることで、敬称と名前の区切りがはっきりし、点訳に落とし込んだときにも誤解を生まない。
翻訳から点訳へ――両方を見据えた工夫こそが、読み手に寄り添う自由な点訳につながると、私は考えている。