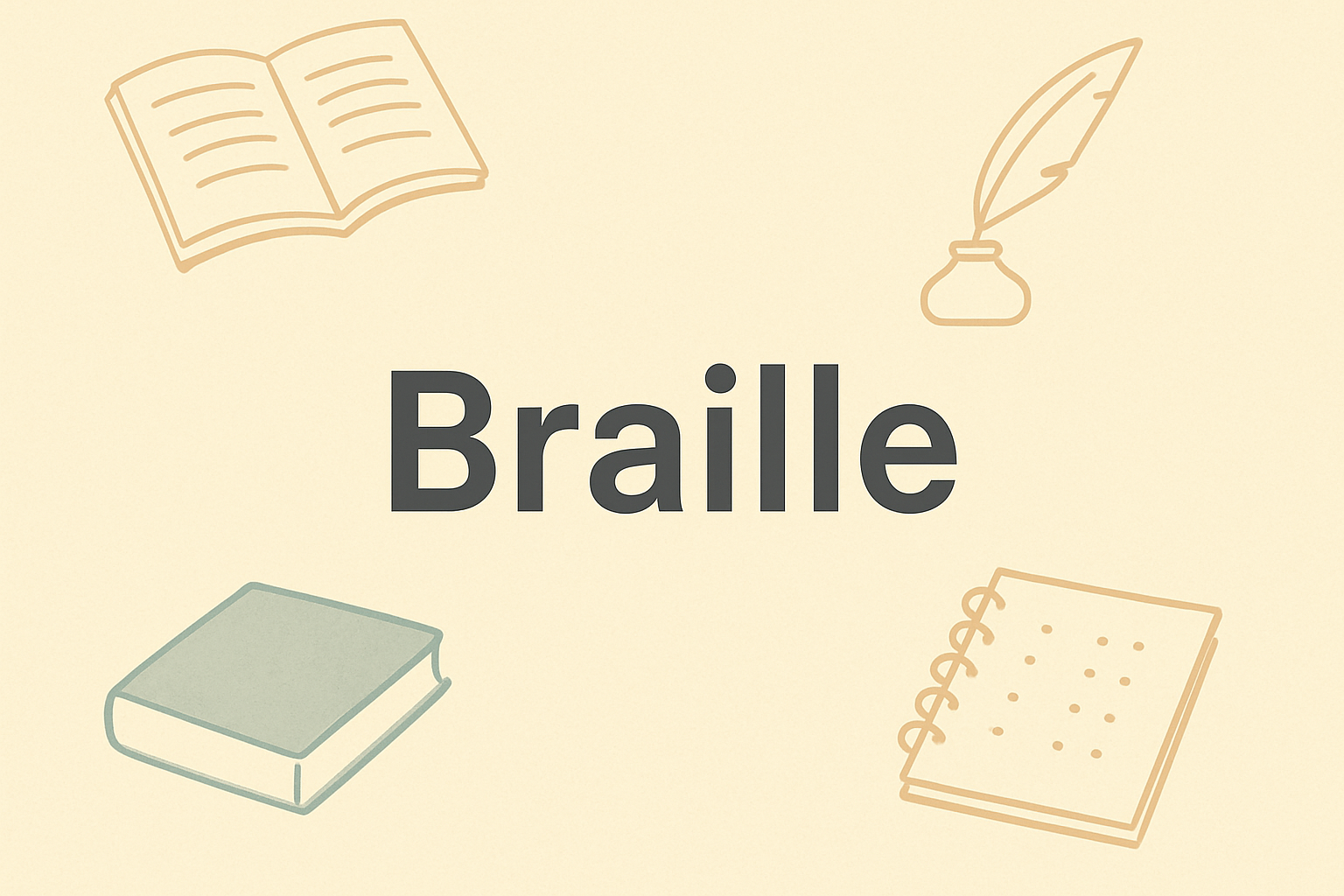点訳を学び始めて、すぐに気づいたことがある。
講習で繰り返し語られるのは——「手引きに従うこと」。
文法的に分析し、決まりに当てはめろ。
——でも、そこに「読み手」はいない。
点訳は、机上の演習ではなく、指でたどる読者のためのものだ。
読み手がすっと意味をつかみ、迷わず進めるように。
そのための“形”として点字があるはずなのに、
「手引きに忠実であること」だけが目的になってしまう。
「規則を守っているか」が優先され、
「読みやすいかどうか」が後回しにされる。
それは点訳というより、文法論にすぎない。
言葉としての息遣いが、そこから抜け落ちてしまう。
僕は、読み手のために打ちたい。
文章のリズムや呼吸を点に込めたい。
句読点ひとつ、改行ひとつに工夫を凝らしたい。
だからこそ思うのだ。
「手引き」は必要だ。点訳ボランティアがまず開く最初の「道しるべ」だ。
だがそれは“参考書”であって、“戒律”ではない。
もし手引きを盾にして読み手を忘れるのなら、そんな使い方こそいらない。
点字は点の並びにすぎない。
だが点訳は、誰かが読むために、新しい文字で文章をもう一度つくりなおす営みだ。本来もっと自由で、生きた営みのはずだ。
読み手に寄り添い、言葉を生きた形に変えていくこと。
そのために僕は、点字を学んでいる。
だからここで声を大にして言いたい。
——「点訳の手引き!? そんな使い方なら、いらない!」