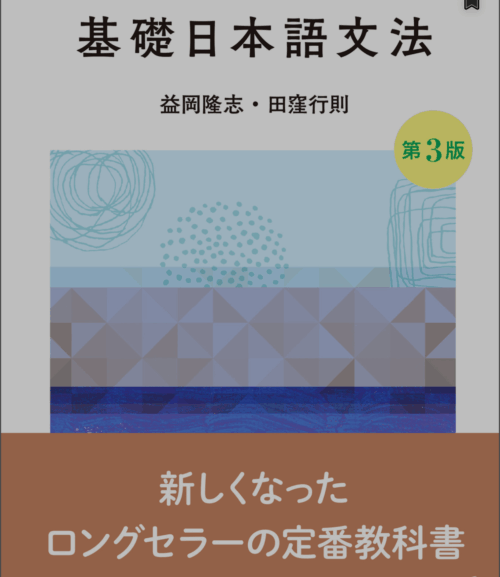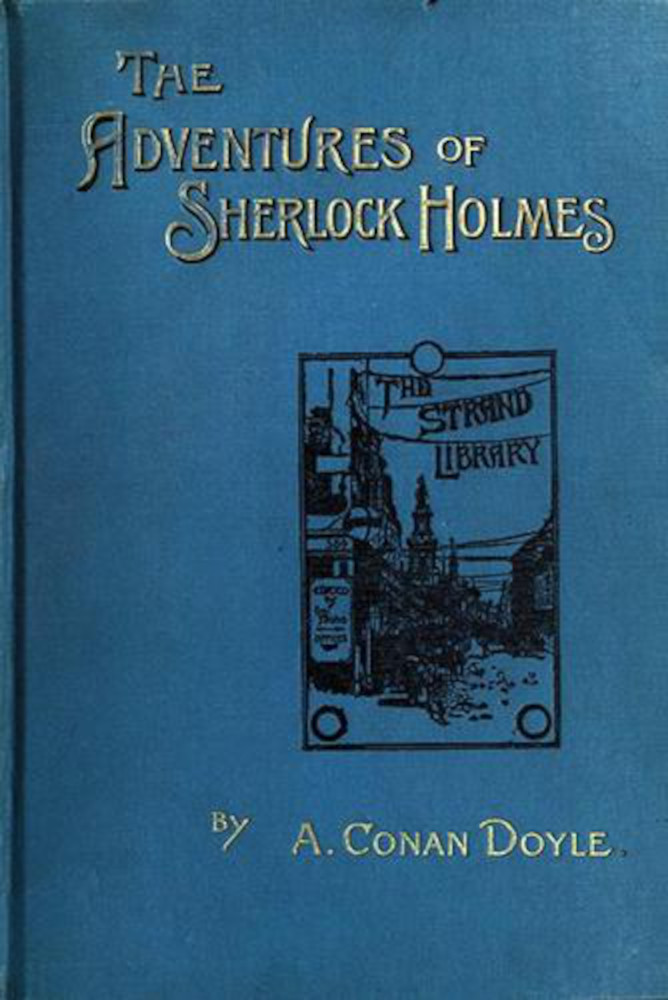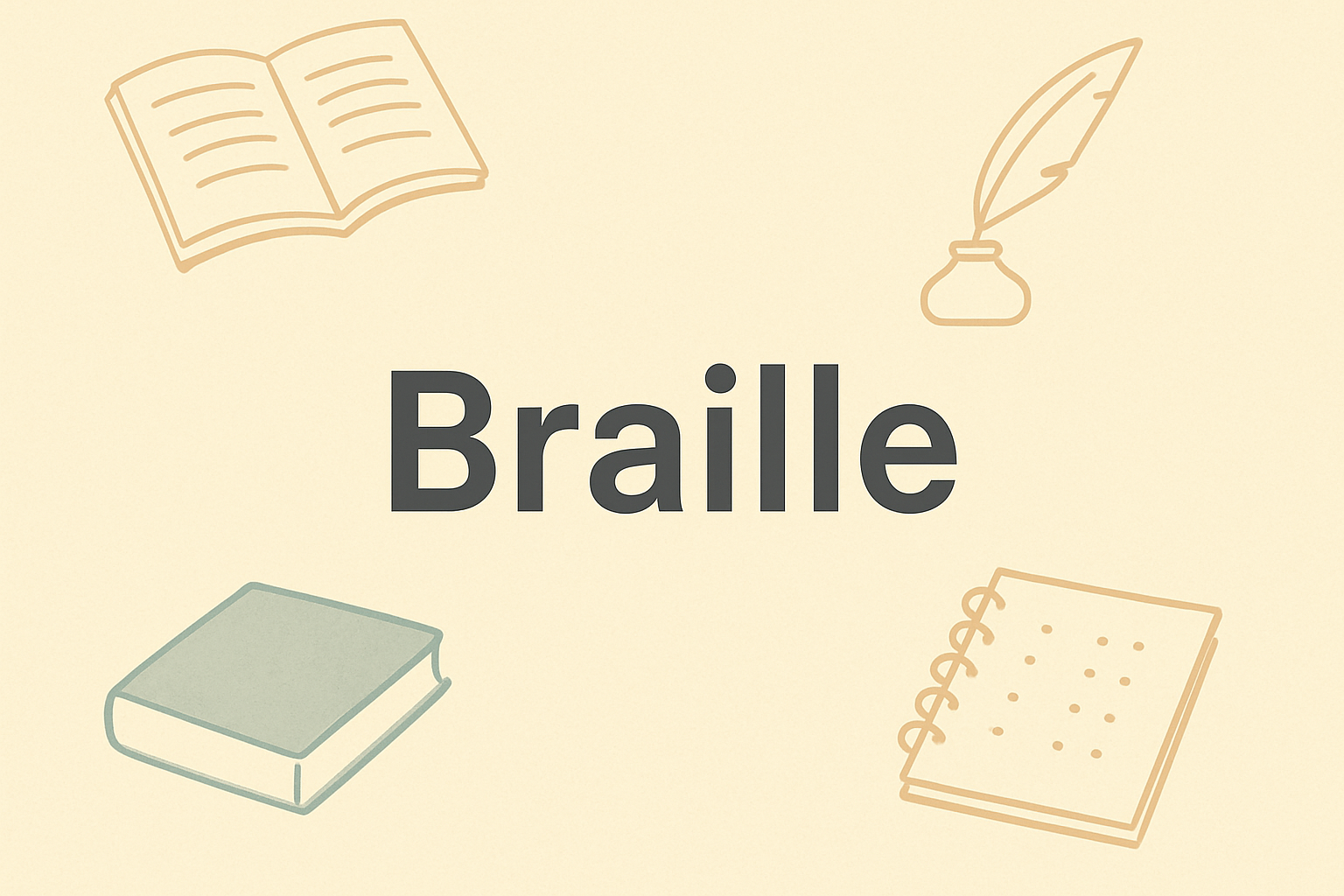ラボ流では、読み手目線、点訳者の負担軽減のために、「形式名詞」について自然な区切り(ます空け)を実現するため、『点訳の手引き』とは異なる基準を定めています。
続け書きの原則
形式名詞については、『点訳の手引き』では、『実質的な意味が薄れた名詞(形式名詞)も自立語なので前を区切って書く』としています。
しかし、ラボ流では『名詞=自立語なので』という「文法上の理由」だけで、前の語と区切って書くことは許容しません。
なぜなら、『日本点訳表記法』P31に述べられた第2の原則「切れ続き」の基本的な理念(=複合語以外にも通じる考え方)
『・・・自立語内部にある独立性の強い意味のまとまり(区切って書き表した方が意味の理解を助ける構成要素)で区切る・・・』
に反すると考えています(補助動詞についても同様です。)
- しかも、下記理由により、前の語と区切るための外形的基準としての一律的な判断には耐えられないと思われます。
- 形式名詞か否かは異なった扱いをする学説があること
- 補助的な品詞であるため辞書によってはその表記がないこと
したがって、たとえ「文法上は」自立語であっても、意味が希薄で、修飾要素なしでは使えない名詞(上記『自立語内部にある独立性の強い意味のまとまり』とはいえない名詞)であれば、前の語と「続け書き」することを原則とします。
漢語の形式名詞
区切っても意味がわかりにくいので、原則、前の語と「続け書き」する。
「以上」「以前」「点」「方」「前(ぜん)」「他(た)」「節(せつ)」「輩」(『点訳の手引き 第4版 p61より抜粋』)
※「以上」「以前」など、「以〜」という言葉には、接続詞としての用法があることに注意
和語の形式名詞
「和語」であっても、意味が極めて弱く辞書によっては接尾辞の性格を持つ名詞や、連体詞の後に続く形式名詞は「続け書き」する。
「この前」「この間」「この期(ご)」この程(ほど)」「この度(たび)」「そのくせ」「その上」「その内」「その儘」「どの道」「我が家」「我が儘」(『点訳の手引き 第4版 p61より抜粋』)
判定詞「だ」を伴う形式名詞「の」「よう」
判定詞「だ」「である」「です」の前に付いて、助動詞「の・だ」「よう・だ」になる場合は、形式名詞が助詞の働きをしているので、「続け書き」を原則とする。→ 「助動詞」参照
- ただし、「〜(の)ようである」「〜 (の)ようであった」など、4拍以上になる場合は、「よう」の前で「分かち書き」許容する。
- 補助動詞「ある」「あった」(2〜3拍)の前で区切るよりも優先する(リズムを考慮)。
- 「の」は、助詞としての性格が強いので、前の語と「続け書き」する
判断材料
- 前の語と一体になって「慣用句」や「連語」として辞書に掲載されている
- 2拍以下で、発音だけでは意味がわかりにくく、誤読の恐れがある
分かち書き
補足句(節)・副詞句(節)
形式名詞は、長い「補足句」「補足節」(CP)や、「副詞句」「副詞節」(TP)の後に続いて、まとまった「句」「節」を作る働きをする場合がある。
そのため「続け書き」を原則とする一方で、長い「節」「句」をまとめている場合は、「分かち書き」を許容する。
補足句(節)(CP)を作る形式名詞
「こと」「の」「ところ」
補足句(Compliment Phrase)として、原則、形式名詞として「続け書き」する
「こと」「ところ」については、主語と述語を伴った「補足節」や、長い「名詞句」の全体にかかる場合は、「分かち書き」を許容する。
私は|彼女が|結婚|したことを|知らなかった。(採用)
→ 「彼女が|結婚した|ことを」を許容するが、リズムを考慮し不採用
彼は|値段が|高いのが|欲しいようだ。(採用)
泥棒は|走り続ける|ところを|捕まえられた。(採用)
→ 「走り続ける」という複合動詞が7拍のため、形式名詞の前で区切る
副詞句(TP)、副詞節を作る形式名詞
意味範疇によって、多くの形式名詞がある。
1.時を表す副詞句・副詞節
「時(に)、」「おり(に)、」「間(に)、」「うち(に)、」「後(に/で)、」「前(に)、」「最中(に)、」「際(に)、」「場合(に)、」「たび(に)、」
次の|会議の|時(に)、|また|議論|しましょう。(副詞句)
雨が|止んだ|後(に)、|出かけた。(副詞節)
2.原因・理由を表す副詞句・副詞節
「ため(に)、」「おかげ(で)、」「せい(で)、」「あまり、」
事故の|ために|列車は|30分ほど|遅れた。(副詞句)
事故が|起きた|ために、|列車が|止まった。(副詞節)
3.様態を表す副詞句
「通り(に)、」「よう(に)、」「代わり(に)、」「他(に)、」「ついで(に)、」「まま(で)、」
私は|教科書の|指示(の)|通りに|実験を|行った。(副詞節)
⚠️判定詞「だ」は連体形「の」に活用し、省略できる。
私は|実験を|する|代わり(に)|レポートを|提出|した。(副詞節)
「ように」は形式名詞「よう」の意味が極めて弱く、助動詞(形式名詞+判定詞)「ようだ」の連用形とみなして、続け書きする。
私は|雑誌の|モデルのように|なりたい。(副詞句)
⚠️判定詞「だ」は連体形「の」に活用するが、形式名詞「よう」の意味が極めて弱く、省略できない。
私は|雑誌の|モデルが|歩くように|歩きたい。(副詞節)
4.その他の副詞句
「一方(で)、」「反面、」「限り、」「くせ(に)、」「ほう、」
彼は|偉大な|反面(で)、|敵は|多い。(副詞句)
彼女は|勉強|して|いる|くせ(に)、|成績が|悪い。(副詞節)
類似表現と省略
形式名詞と接尾辞
形式名詞は文法上「名詞」であるから、その前に「の」を入れることができる場合が多い。
しかし、前の名詞に直接接続した助詞「の」が入ると意味が通らない形式名詞は、接尾辞的なので「助詞」として扱う。
- 「ほど、」副助詞
- 副助詞〔名詞「ほど(程)」から。中世以降の語
- 「くらい、」:副助詞
- 名詞「くらい(位)」からの転。中世以後生じたもの。「ぐらい」の形でも用いる
- 「以前、」「以上、」「以外、」など:名詞
- 4字以上の漢語の一部表記される場合は、「複合名詞」の後項として扱い、真ん中(形式名詞の前)で「切れ続き」する。
- 連体詞の後に続く場合は、原則通り「続け書き」する
戦争ほど|悲惨な|出来事は|ない。(「ほど」は名詞「程」から副助詞)
今年の|8月くらい|暑かった|ことは|ない。
欧州では|19世紀|以後(は)、|各地で|革命が|起こった。(複合名詞「切れ続き」)
日本は、|平成|以前(は)、|経済|成長|して|いた。(複合名詞「切れ続き」)
修飾要素が省略できる形式名詞
文脈から明らかな場合は、形式名詞の修飾要素を省略できる。
この場合は、文脈上、続けて書くとその修飾要素の判定を妨げる恐れがあるので「分かち書き」する。
(あなたの)|おかげで|助かりました。
今日は|私が|(彼の)|代わりに|来ました。
この作業は|さっきの|(作業の)|ついでです。
ポイント
- 形式名詞は「続け書き」を原則とする
- 形式名詞の前で「分かち書き」が許容される場合
- 判定詞「〜だ」の活用形を伴う形式名詞で、4拍以上になる場合
- 「山の|ようである」「面白かった|そうです」など
- その形式名詞が、長い「補足句(節)」「副詞句(節)」を形成する場合
- 次の|会議の|時(に)、|また|議論|しましょう。(副詞句)
- 雨が|止んだ|後(に)、|出かけた。(副詞節)
- 2字漢語の形式名詞で、4字以上の漢語の一部として表記される場合
- 欧州では|19世紀|以後(は)、
- 日本は、|平成|以前(は)、
- 文脈上、その形式名詞の修飾要素が省略されている場合
- 今日は|私が|(彼の)|代わりに|来ました。
- この作業は|さっきの|(作業の)|ついでです。
- 判定詞「〜だ」の活用形を伴う形式名詞で、4拍以上になる場合