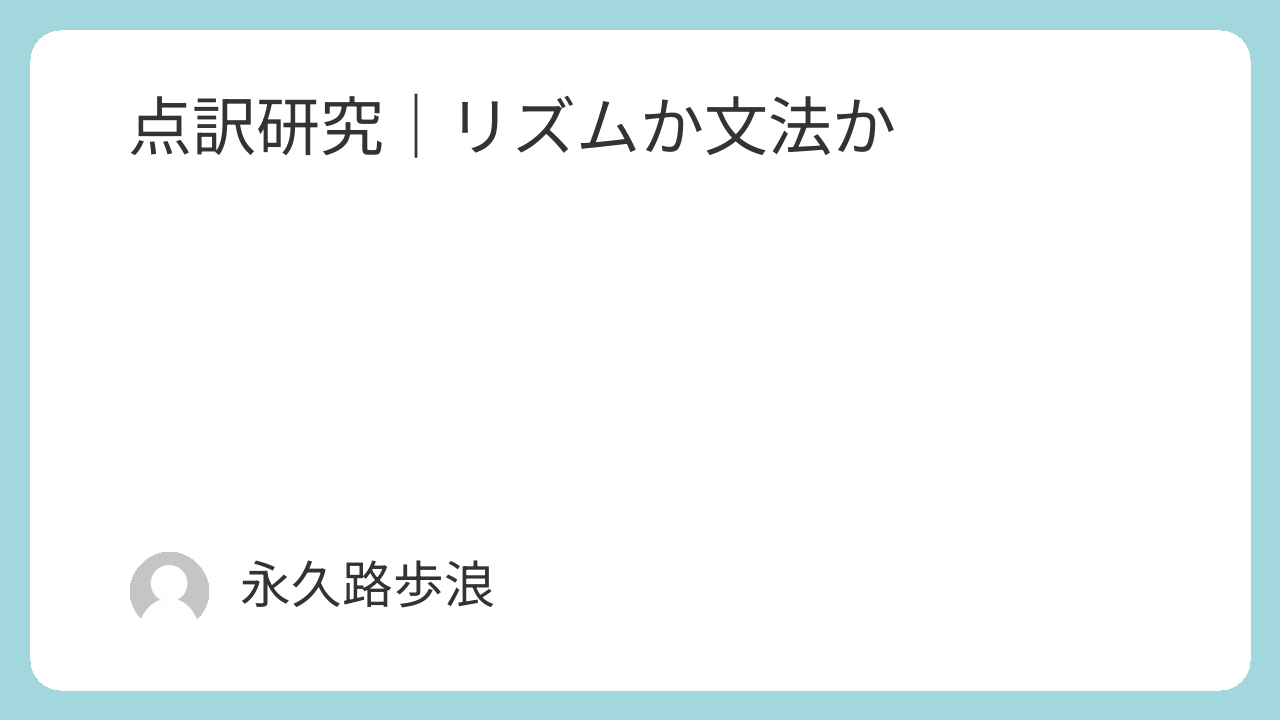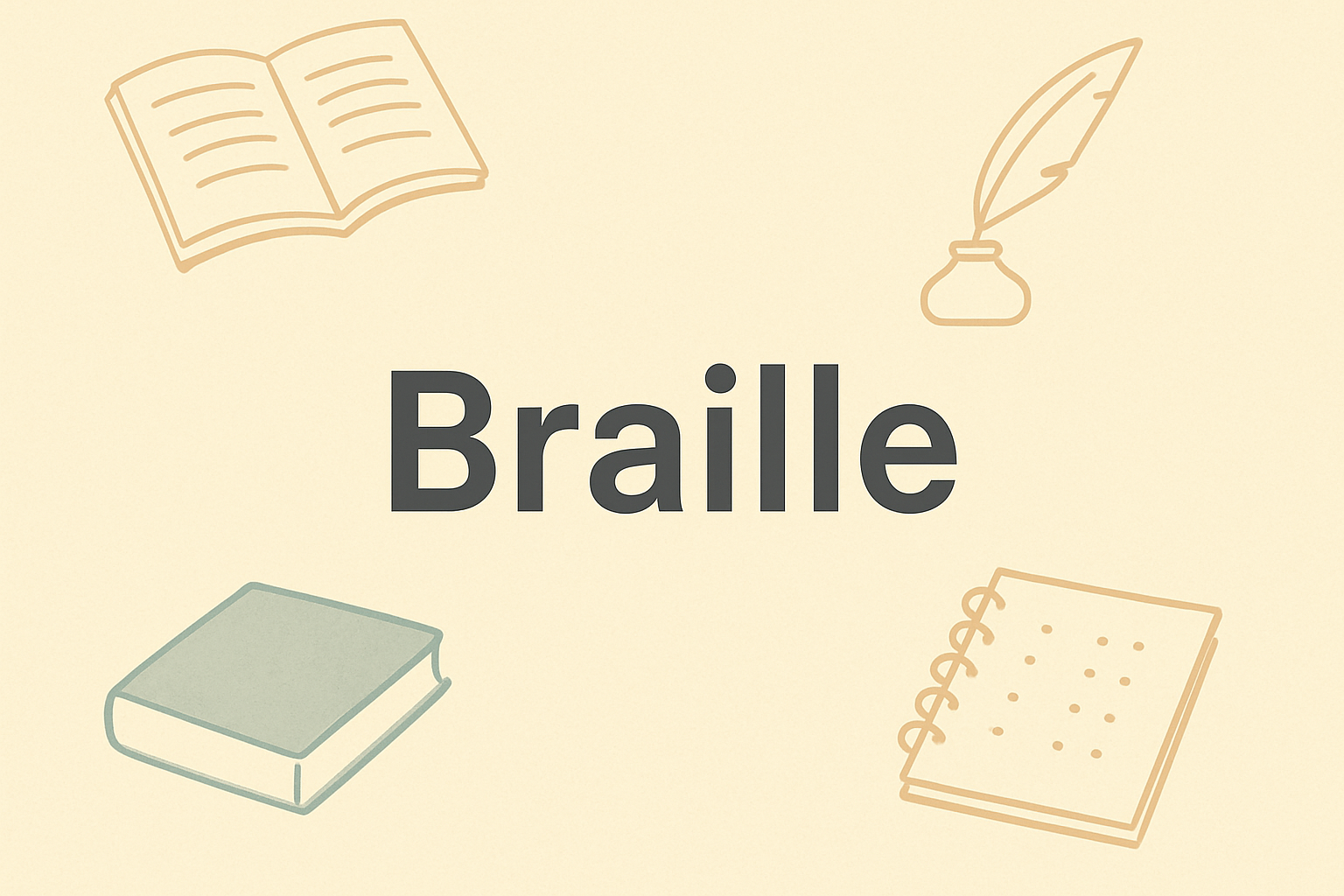気づいていたのだ。
ラボ流では、8拍なので、どこかで区切らなければなりません。
もちろん、8拍でも無理に区切ることはせず、文章の「意味のまとまり」を優先して、全て続けて書くことも考えられます。点訳者としては、その方が楽かもしれません。
しかし、文法的に区切る根拠がある限り、読み手の負担を考えたラボ流の基本精神「7拍基準」は遵守すべきです。
そこで、文法で区切るとすれば、『気づいていた』が、複合動詞(「気づいた」+補助動詞「いる」)という、一つの意味のまとまりなので、まず連語(判定詞)「のだ」の前で区切りたいところです。
気づいていた|のだ。
しかし、拍数によるリズム重視でいけば、「のだ」という2拍の前で区切るよりも、「3・4・5」拍を一つのリズムとして、次の区切りの方が自然です。
気づいて|いたのだ。
ラボ流は「文法よりもリズム重視「文法は、分かち書きするときの根拠にすぎない」という哲学の上では、「いた」という補助動詞の前で区切ることも許容されます。
ただし、注意したいのは、文章としてはあくまで『気づいていた』で、一つの意味のまとまりです。
リズムを重視するあまり、この意味のまとまりが崩れ、ラボ流の基本精神である「誤読の可能性」があってはいけません。
何度か口に出して読んでみて、この可能性がないということを確認した上で、「気づいて|いたのだ」を採用すべきと考えます。
(追記)「置かれていたのである」は、「6+4」拍ということで、次のように『置かれていた』という意味のまとまりで区切ります。
置かれていた|のである。
つまり「のだ」という2拍の前で区切るのはリズムが崩れますが、しかし、「のである」という4拍になれば、「6+4」という区切りになって、リズムが崩れることがありません。
この違いが、「文法は区切る補助にすぎない」という哲学の現れです。
一見不自然な区切りにも見えるかもしれません。
しかし、『いたのである』という補助動詞の前で区切ることは、6拍という長くて弱い意味のまとまりを作ることになります(本来の自立語といえる要素がない!)。
置かれて|いたのである。
この表記を是としておくと、漢字表記の1文節『居たのである』というようなまとまった意味がないにもかかわらず、今後「居た」という誤読の可能性が生じる場合が考えられるのです。