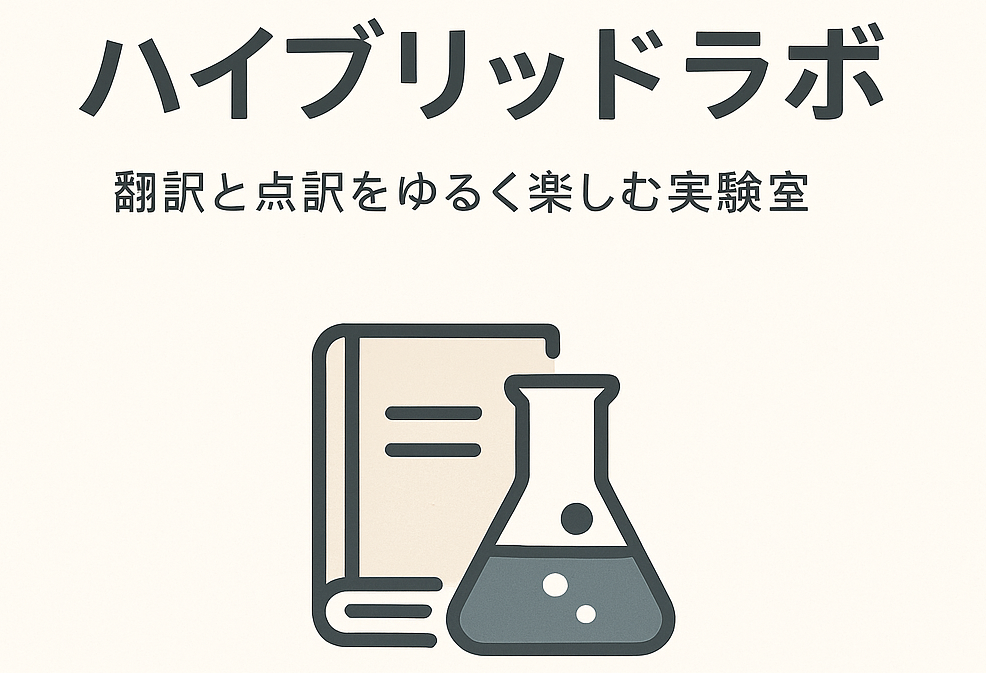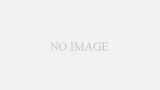ラボ流『3層フレーム』と『3段階基準』
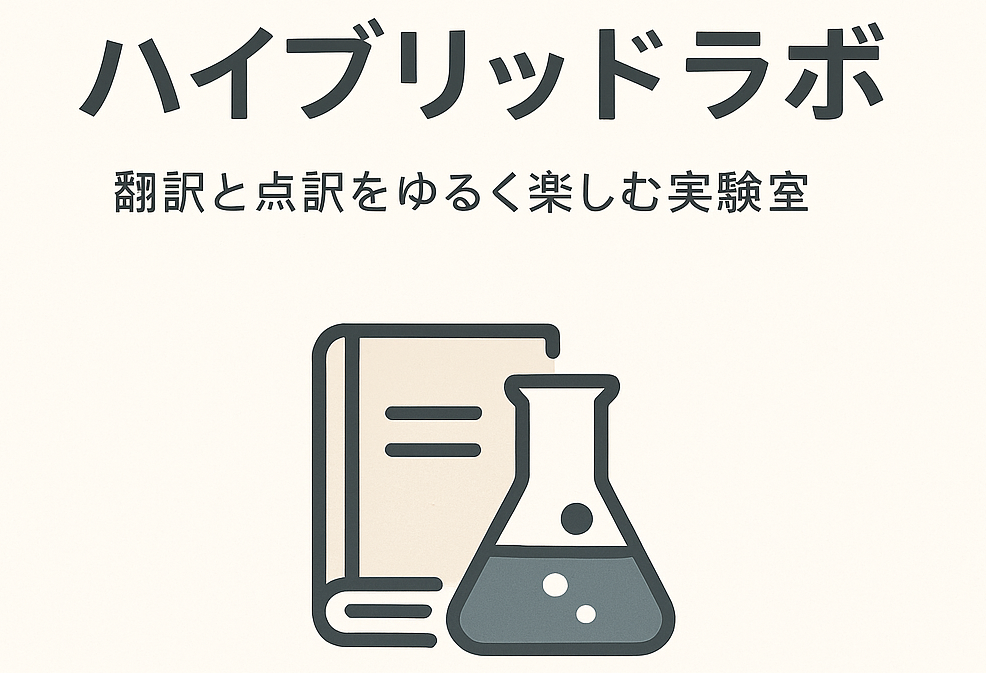 斜め上から見る点訳論
斜め上から見る点訳論
2025.09.03
位置づけ
- 日本点字表記法:点訳の憲法(全体を律する最高規範)
- 3層フレーム:憲法の理念を実務に落とし込む、点訳判断の枠組み
- 3段階基準:具体的に運用するための細則
3層フレーム(点訳判断の大枠)
第1層:文節分かち書き(日本点字表記法 第1の原則「分かち書き」に対応)
- 文節の最小単位
- 自立語のみ
- 自立語+助詞・助動詞
- 自立語+接頭語・接尾語・造語要素
- 複合語
第2層:切れ続き(日本点字表記法 第2の原則「切れ続き」に対応)
- 第1層(文節分かち書き)の例外
- 文節が長くなると、表音式表記では意味の理解を妨げる
- 俳句の5・7・5に由来する7拍限界説
- 7拍以上の複合語や固有名詞
- 切れ続きの言葉の意味
- 区切って書くが(切れ)、意味のまとまりとしては続いている(続き)
第3層:読み手目線(ラボ流独自の原則)
- 点字は、語の形で判断する「表語式表記」ではなく、発音で判断する「表音式表記」であることを常に意識する。
- 墨字では誤読しないが、点字では誤読しやすい箇所を救済することを目的とした例外を、適宜、認める。
- 可読性・リズム・理解のしやすさを優先して区切る箇所を判断する
- 可読性;誤読の防止
- リズム:拍数・息継ぎ
- 理解のしやすさ:意味のまとまり、慣用・慣習など語句の識別性
- 読み手にとって自然かどうかで最終判断。
3段階基準(分かち書き・切れ続きの具体的運用)
- 5拍以下
- 文節の標準拍数(3〜5拍)で、原則、続け書きする。
- 6〜7拍
- 原則、続け書き
- 『手引き』では文法的判断によって、その前で区切って書くこととされる品詞でも、表音式表記の観点から、独立した意味が弱い次の品詞は、原則続け書きする
- 形式名詞の前
- 補助動詞の前
- 指示詞の後
- 指示連体詞「これ、それ、あれ、どれ」の後
- 指示副詞「こう、そう、ああ、どう」の後
- 上記品詞に区分する学説(言語学)が一つ以上あるもの
- (例外)第3層を考慮した場合、区切って書くことができる。
- 連体詞の後に、2字以上の漢語や名詞句など、独立した意味の強い語が続く場合
- 8拍以上
- 原則、区切って書く
- 長い触読による読み手の負担を軽減する
- (例外)自立語が一つしか含まれておらず、誤読の可能性がない場合は、長い触読の負担よりも意味の理解を優先して続け書きする。
- 区切る箇所は、第3層を基準とする → 第3層の手がかり