講習で学んだことや日々の気づきを手がかりに、点訳の制度やルールを一歩引いた「斜め上から」見直しています。
実務に追われていると見えにくいと思われる問題を拾い上げ、「本当に読み手に役立つか?」という観点から記事をまとめています。
そのため、『点訳の手引き』にできる限り準拠しながらも、「ラボ流」として独自の工夫を凝らしています。
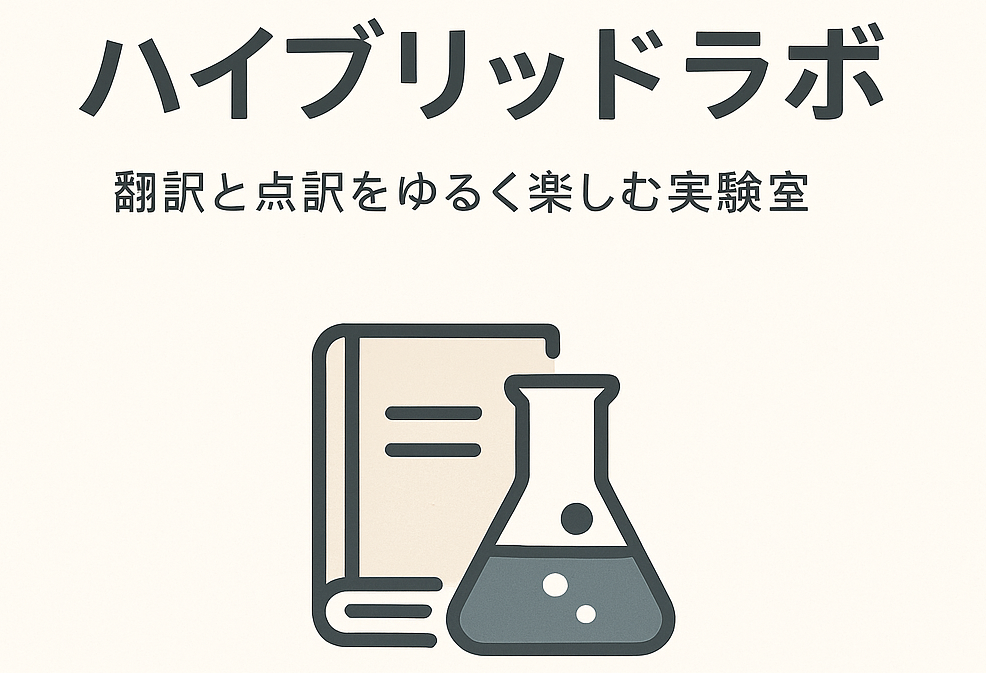 斜め上から見る点訳論
斜め上から見る点訳論 3層フレームの第3層の具体的適用
点訳する際は、まず3段階基準を使うが、迷ったときは、3層フレームの第3層に照らして最終判断する(3層フレームについてはこちら💁♂️)原則として自立語と助詞・助動詞は続け書くが、未知の固有名詞・制度名・地名・会社名など、明らかに「読み手にと...
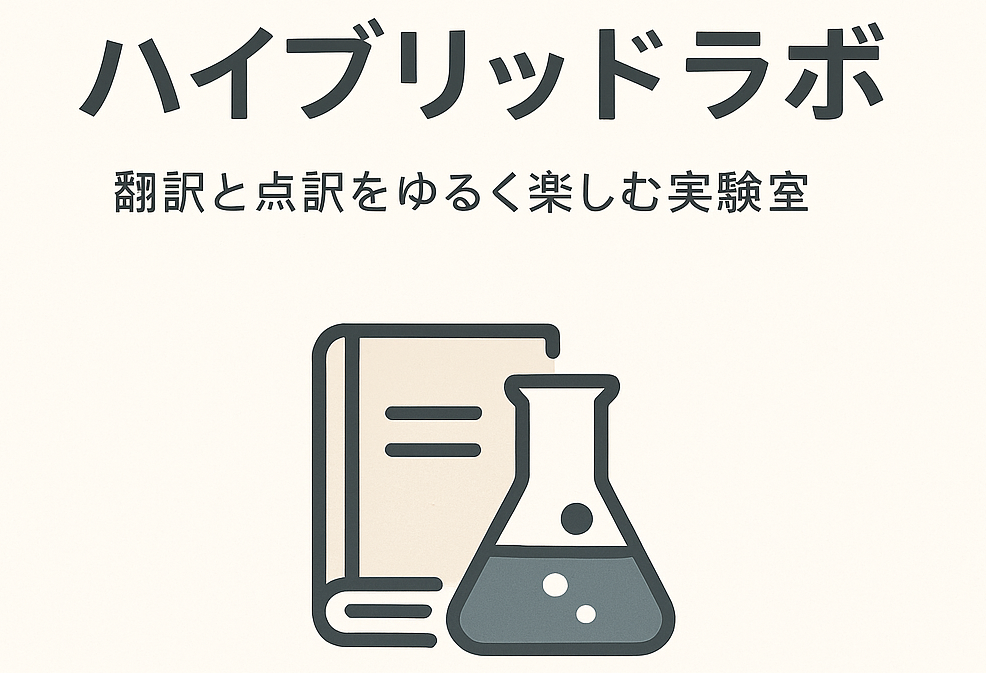 斜め上から見る点訳論
斜め上から見る点訳論 第3層|切れ続きをする箇所の手がかり
第3層を考慮して、例外的に区切る場合の形式的な手がかりラボ流では、文節分かち書きで8拍を超える場合は、原則として、次の箇所のいずれかで区切って書く。拍数(3〜5拍)、読んだときのリズム、息継ぎなどを考慮し、具体的事例ごとに読み手目線で自由に...
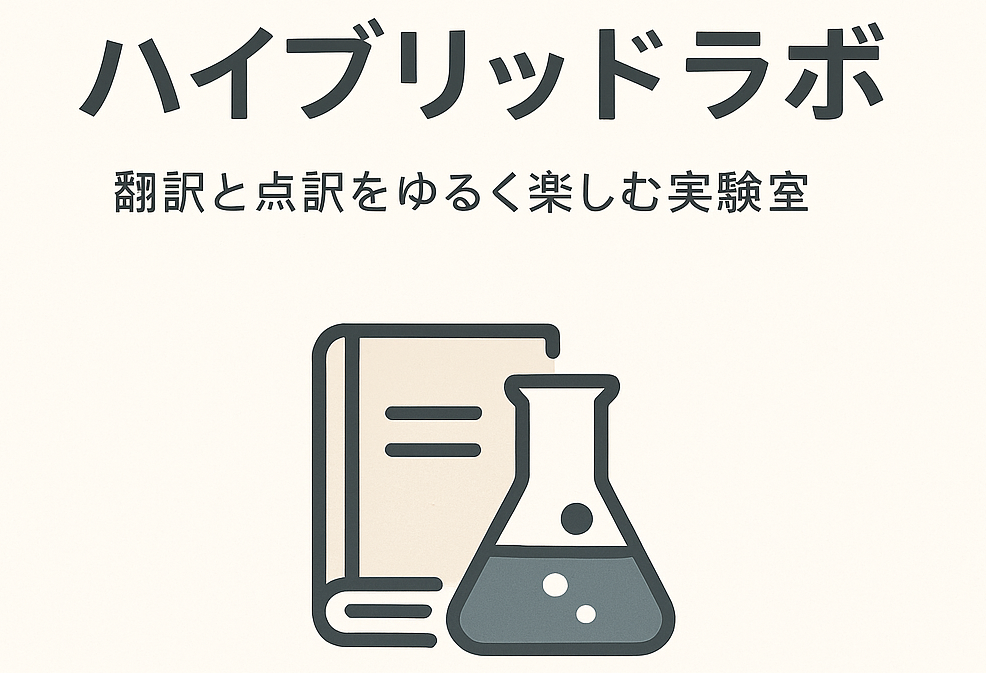 斜め上から見る点訳論
斜め上から見る点訳論 ラボ流『3層フレーム』と『3段階基準』
位置づけ日本点字表記法:点訳の憲法(全体を律する最高規範)3層フレーム:憲法の理念を実務に落とし込む、点訳判断の枠組み3段階基準:具体的に運用するための細則3層フレーム(点訳判断の大枠)第1層:文節分かち書き(日本点字表記法 第1の原則「分...